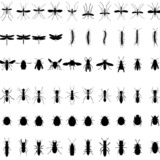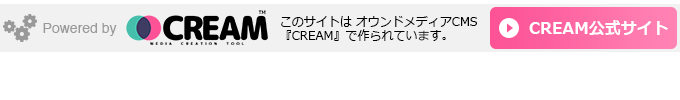ガスが切れてしまった、長い間使っていなかったために火が付かなくなってしまった、禁煙したので必要なくなった。そのようなライターを普段どのように捨てていますか?ガスが切れたんだから、普通にゴミとして捨てて良いと思いがちですが、実はライターにはきちんとした捨て方があります。そして、決まりを守らないと自分や作業員の方々が火災や爆発に巻き込まれるなど、大事故につながる危険があります。
ここでは、安全で正しいライターの処分方法について解説していきます。
ライターの処分方法5つ

ライターの処分方法|その1 ■①100円ライターの捨て方
100円ライターはコンビニやスーパーで気軽に買うことができる上に、簡単にタバコや花火等に火をつけることもできます。経済産業省によれば、日本では年間約6億本のライターが売買されており、その大半が100円ライターであるほど人気があります。
100円ライターはノベルティーなどでもらうこともあり気軽に使える一方で、ガスがすぐに無くなってしまったり、ガスはあるのに石の部分が回らなくなり使えなることもよくあります。
使えるけれどもいらなくなった場合、故障して使えなくなった場合にも、処分するためには中の液体ガスを全て使い切り、さらに念のためガス抜き作業を行う必要があります。経済産業省が出しているライターの正しい捨て方のパンフレットには、使い捨てガスライターは「ガス抜きをして」捨てるように書かれています。
完全に中のガスを使い切る方法ですが、まず、作業は火の気の無い外で行います。ベランダや庭などの風の流れがある場所を選んでください。出たガスを自分で吸わないように、作業する人は風上に立ち、風下には誰もいない状態で作業を行いましょう。
そして、ライターのレバー部分をずっと押し続けます。小さな音ですが「シュー」「スー」というガスが出ている音が聞こえる場合もあります。音がしなくてもガスは出ていますので、レバーを押し続けてください。もし火がついてしまったら、火は消し、レバーだけ押し続けましょう。ガスの量を調節するレバーをプラスのほうに移動させるとより早くガスが出ます。
レバーを押し下げていればガスが出ますが、ガスの残りの量によっては一日くらい押し続けていないと中身が空にならない場合があります。そういった際に最も手軽な方法は『喫煙者である知人にあげる事』でしょう。
どうしても自身で処分する必要がある場合は長時間になるととても指で押さえきれませんので、そのような場合は輪ゴムでレバーを下げたままにしておいたり、ガムテープなどでレバーを固定したりしておきましょう。その場合、子どもやペットがライターで遊んでしまわないように気を付けてください。
中のガスが全て出たと思ったら、確認のために火をつける動作をしてみましょう。火が全くつかなければ、自治体のルールに沿って捨てることができます。
個人での分解は危険
インターネットで100円ライターの捨て方を検索すると、「分解して金属部分とプラスチックに分けて捨てましょう。」と書いてあるサイトがあります。しかし、ライターの分解は非常に危険です。こじ開けたり、分解したりする時に火花が出て、それが残りのガスに引火し爆発する可能性があります。
キリや尖ったもので100円ライターの横に穴を開けて、液体ガスを出すことも大変危険です。中のガスを出しきれないようであれば、捨て方を自治体に相談しましょう。
ライターの処分方法|その2 ■②注入式ガスライターの捨て方
注入式ライターには、ガスを入れるタイプと、ジッポ・ライターのようにオイルを入れるタイプがあります。ここでは、ガスを入れるタイプの捨て方について説明します。注入式ライターも、100円ライターと同様ガス抜きをする必要があります。こちらも野外の通気性の良い場所で行い、風上に立つようにします。
ライターのガス注入口を、先の細い棒で押します。メガネのネジなどを調節する時のドライバーがあると、大変作業がしやすくなります。先の細いものでガス注入口を押すと、「シュー」「スー」という音が聞こえる場合がありますが、これはガスが正常に抜けている音です。
音がしなくなったら、試しに火をつけてみましょう。火がつかなければガスは全て抜けています。火がついたらまだガスが残っているので、再び同じ作業をしてください。
ライターの処分方法|その3 ■③ライター用ガスボンベの捨て方
ライターに入れるガスのガスボンベを捨てる時も、そのままゴミとして捨てずに必ず野外でガス抜きをしてから捨てましょう。ライター用ガスボンベのガスの抜き方は、ボンベのキャップを外してノズルを下にし、地面に押し付けます。コツとしては、垂直にノズルを地面に当ててしまうとガスが出なくなってしまうので、少しだけ斜めに傾けるのがポイントです。
ガスを出すと、ボンベ自体が冷たくなりますが、自然な作用ですのでそのままガスを出し切って大丈夫です。全て出し切るまでに、長い場合は数分かかります。ノズルを地面に押し付けても「シュー」「スー」という音が出なくなれば作業完了です。
100円ライターや注入式ガスライターの場合は、最後に火をつけてガスが全部出たかをチェックしましたが、ライター用ガスボンベの場合は火をつけての確認作業は行いません。万が一ガスが残っていた場合、大変危険ですので、絶対にライター用ガスボンベには火を近づけないでください。
また、以前は穴を開けてゴミに出すよう指導していた自治体でも、穴を開ける時に火花が出ると爆発して大変危険なため、近年は穴は開けないでゴミに出すように捨て方が変わってきています。ガスを出し切ったライター用ガスボンベは、それぞれの自治体の決まりに沿って捨てましょう。プラスチックのキャップがあれば、それは外してプラスチックごみとして出します。
自治体による捨て方の違い
例えば、横浜市は30センチ以上のボンベであれば、「粗大ゴミ」、それ以下のエアゾール缶であれば「スプレー缶」の日にゴミに出します。ゴミに出す時は、中身がわかるように透明か半透明の袋に入れる必要があります。また、東京都の場合はガスを出し切ったら、中身がわかる透明な袋に入れて「資源ごみ」の日に出します。
北海道札幌市は、平成29年7月からライター用ガスボンベのゴミ出しルールが変わりました。穴は自分で開けずに、中がわかる透明な袋に入れて「燃やせるゴミ」の日と同じ日に出すようになりました。もしも、何かの事情でライター用ガスボンベの中身が出せない場合は「一般社団法人 日本エアゾール協会」に相談してみましょう。
ライターの処分方法|その4 ■④タバコを吸う人にあげる
ライターは無理に捨てなくても、タバコを吸う人が周りにいればプレゼントするのも一つの方法です。100円ライターは中身がすぐに無くなるので、使う人にとっては使いかけであっても有り難いものです。この際、ライターは郵便では送ることができませんので注意が必要です。誰かにあげるのであれば手渡しするのが良いでしょう。
ライターの処分方法|その5 ■⑤ライターを売る
ライターを売って処分するとき|その1 高級ライターの買い取り相場
もし処分しようとしているライターが高級ライターであれば、業者が高く買い取ってくれる場合があります。
goro's(ゴローズ)やchrome hearts(クロムハーツ)といったジュエリーブランドのライターであれば、多少傷があっても数万円で買い取ってくれる可能性が高いです。また、ダンヒルやグッチ、カルティエといった昔からのファッションブランドライターは、物により値段は上下しますが、数万から高いものでは10万円ほどで買い取ってくれるものもあります。
成功者の証とも言われているデュポンのライターは、限定モデルであるエクスプレスやアンダルシア、カタコンベを中心に高く売れます。数万円から15万円ほどの値段が相場となっています。
ジッポのライターは、保証書や証明書があるとより高額で買い取ってもらえます。ガンダムなどのアニメをモチーフとしたものや、タバコメーカーとのコラボ、復刻限定モデルなど、特別なものであれば1万円から1万5,000円ほどになるでしょう。
ライターを売って処分するとき|その2 ライターが売れるかどうか?を自宅で確認!
「ブランド物っぽいライターだけど、売れるかどうかわからない」という方には、自宅でリサイクルショップの買取り査定額がわかる「おいくら」というサービスがおすすめ。
利用方法は簡単で、メーカー名や購入時期などを記入するだけ!小さなライター1つだけを持ってリサイクルショップを回らなくても、自宅にいながら「そもそもこのライターは売れるの?」という1番気になるところがわかります。
ライター以外に「もしかしたら売れるかも」となかなか捨てられない家具や家電・衣類などが部屋を占領していませんか?この機会に査定してもらって、スッキリ新年を迎えましょう!

全国対応!不要品買取のお店を探すなら【おいくら】
電話番号や詳細な住所まで記入する必要はなく、しつこい営業メールが来ることもなかったのでおすすめです。「ライターに値段がつくかどうか?」という最も気になるポイントがサクっとわかります。
ライターを売って処分するとき|その3 ライターの販売規制について
平成23年9月から、使い捨てライターや、チャッカマンのような燃料と点火する部分が一体になっていて、本体にプラスチックがついているものは、経済産業省の「PSCマーク」がついていないと売れないという規制が施行されています。新しい基準である「PSCマーク」をつけることができるライターは、子どもが間違って操作しないような「チャイルドレジスタンス機能」をつけています。
オークションやネットショップなどで、第三者にライターを売ろうとしている場合は、経済産業省の「ライター規制について」をよく読んでから販売するようにしてください。プラスチックを使用していない金属製のライターなどは、この規制の対象ではありません。
ライターを大量に捨てる場合の方法

ライターを大量に捨てる場合、どうしたら良いのだろうかと悩んでしまいそうですが、自治体のライターを捨てるルールに本数は書かれていません。きちんと中身のガスを抜いて自治体のルールに従って捨てれば、1本であろうと100本であろうと、同じ方法で捨てられます。もし、数が多すぎて自分でガスが抜ききれない場合は、自治体に捨て方を相談してください。
ライターは何ゴミに分別される?

ライターが何ゴミになるかは、各自治体によって違いますが、どこの自治体も必ず使い切ってから捨てることが前提です。例えば、東京都は「金属・陶器・ガラスごみ」ですが、横浜市の場合は「燃やすごみ」として捨てることができます。高知市は、マッチや使っていない花火、ライターは「発火器具・ライター類」という分類になり、(資源・不燃物ステーション)に捨てます。
島根県出雲市は、ライターやスプレー缶、カセットボンベなどは使い切った後は「破砕ごみ」になります。「破砕ごみ」として捨てた後は、破砕機で小さく砕いて、再利用する金属と、処分する燃えるごみに分けています。
ライターを捨てる時にしてはいけないこと

■ガスを抜かないで捨てる
ライターやライター用ガスボンベの中に入っているガスを抜かないで捨てると、大惨事につながるおそれがあります。きちんとボンベの中のガスを出し切って捨てないと、ごみ収集車が燃えてしまう危険性があるからです。
ガスが残っているライターやライター用ガスボンベを普通ゴミとしてそのまま捨ててしまうと、ゴミ収集車の中やクリーンセンター、集積所などでガスが漏れてしまい、引火する可能性があります。そうすると、爆発、火事を引き起こしてしまい、大変危険です。残っているガスが微量でも、火事に発展する可能性は十分にあります。最悪の場合、作業員の命に関わる問題ですので、必ずガスを抜いてから捨てて下さい。
■郵便も宅配便も基本的にライターは運べない
100円ライターに入っているガスは、ブタンガスが主成分の可燃性液化石油ガスです。また、ライター用ガスボンベに入っているガスは、ブタンが95パーセント以上で、残りはプロパンガスが入っています。
日本郵便では、「郵便物として差し出すことができないもの」に「爆発性、発火性その他危険性のある物」として「四、 可燃性ガス」の中にブタンとプロパンをあげています。
ヤマト運輸では、「宅急便で送れないもの」にはっきりとライターとは書いていませんが「花火、灯油、ガスボンベ、シンナーなどの発火性、引火性、揮発性のある物品または火薬類」をあげています。そして、沖縄と他の都道府県を結ぶ飛行機での輸送の場合や、北海道と九州、中国・四国地方を結ぶ飛行機での輸送の場合は、「オイルライター・ライター用燃料」は搭載できないことが書かれています。
このように、郵便や宅配便では自由にライターを運ぶことは禁止されています。郵便よりも多少ルールがゆるい宅配便でも運べる期間が決まっています。そのため、オークション等でライターを販売しようとしている場合は、落札者の方への品物の渡し方は手渡しにするなど、配送法に注意しましょう。
まとめ
今回は、ライターの安全な捨て方について調査しました。
目で見てガスが入っていないと思っても、捨てるときには必ずガス抜き作業をして、自治体のルールに従って捨てるようにしてください。自治体によって、燃えないゴミの所もあれば、必ず「ライター」等と書いて出す必要がある所もあります。どのような方法で出すにせよ、ゴミで出した後に子どもがいたずらしないようにし、捨て方には注意しましょう。
使い切ったから大丈夫と思ってガス抜きをせずに普通ゴミとして捨ててしまうと、ゴミ収集車の中で火災が発生したり、ごみ処理センターで爆発が起こったりしてしまう可能性があります。大惨事を起こさないためにも、ガス抜き作業と確認作業は忘れないようにしましょう。
また、ライターを買い取ってくれるライター専門店もあります。ちょっとお洒落なライターが思いもかけず高値がつくこともあるので、一度ライター買取専門店に相談してみると良いでしょう。