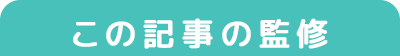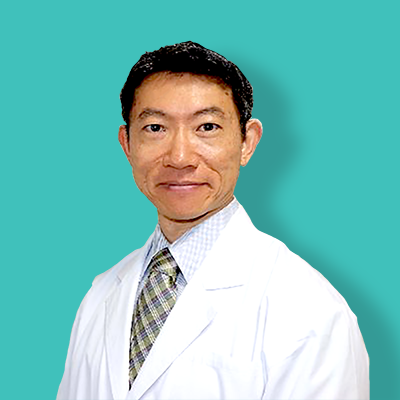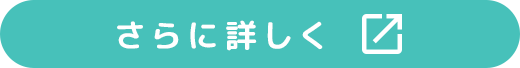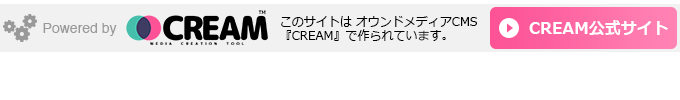クモの巣は、玄関の外灯の周辺や、軒下、庭木などに巣を作ります。一旦クモの巣を作られてしまうと、なかなか自然には壊れませんし、植木がダメになってしまうケースもあるので、放置しておけませんよね。クモの巣を壊しても壊しても、次の日になるとまた同じ場所に巣が作られてしまうので、ホウキで巣を取り払うのもいやになってしまいます。
どのようにすればクモの巣は作られずに済むのでしょうか。クモを家から追い出す方法について調べてみました。
蜘蛛の種類

蜘蛛は他の昆虫の足が6本あるのとは違って、足の数が8本あります。糸を出して巣を作って、巣にひっかかった他の虫を食べる肉食性の虫であることも広く知られています。毒を持つクモもいるので怖いイメージですが、クモの毒はほかの昆虫を殺す程度のものです。全てのクモが、人間を殺すような毒を持っているわけではありません。
クモのタマゴは一度に子どもが数百から数千生まれます。「蜘蛛の子を散らす」と言いますが、まさにそのとおりで一回に非常に多くの子どもが誕生します。クモは1年から3年生きますが、冬場は自分の糸で繭を作って中で過ごします。種類によっては暖かい場所で巣を作るものもいます。
クモの天敵には、ベッコウバチやメジロなどがいます。クモは、ハクビシンなどの哺乳類を駆除する場合と違って、天敵の糞尿を撒くことで巣をつくらないようにすることは残念ながらできません。
クモは世界に4,000種類程生息しています。そのうち、日本にいるのは約1,500種類と言われています。日本で家のまわりに出てくるのは、アシダカグモ、ハエトリグモ、ユウレイグモ、ジョロウグモ、イエオニグモ、オオヒメグモ、ヒラタグモなどです。
■アシダカグモ
アシダカグモは、足を広げると10センチから13センチ程度あります。人の家に住むクモとしては大型の部類で、蜘蛛の巣は作らずに、自分で歩いて獲物を探してつかまえます。姿は気味悪がられますが、ゴキブリやハエをつかまえて食べる益虫でもあります。薄暗い場所や暗い場所が好きで、昼間よりも夜に活動的になります。熱帯や亜熱帯地方、温帯地方に生息していて、全世界で見られるクモです。
家の中では、戸袋や天井裏、壁と家具とのスキマなどに昼間隠れています。公園のトイレの壁に張り付いているのを見ることもあります。寿命はオスが3年から5年程度、メスは5年から7年程度で、夏の間に2回卵を生みます。生まれた子どものクモは、約1年間で親と同じサイズに成長します。
アシダカグモを見たら、すぐに駆除せずに梅雨から秋にかけてはゴキブリを退治してもらったほうが良いかもしれません。アシダカグモを駆除したばっかりに、ゴキブリが出て来るようになってしまったケースもあります。
■ハエトリグモ
1センチ程度の、ぴょんぴょんと飛ぶクモで、名前のとおりハエを取って食べます。また、ハエではなくアリを食べるものもいます。網は張らずに自分が移動して獲物を探すため、日常的によく見かけるクモです。体の割に目がとても大きく、視覚が発達しています。
蜘蛛の巣は張りませんが、常にお尻からシオリ糸と呼ばれる糸を出しているので、獲物を取り損ねて振り落とされてしまっても、地面に叩き落とされるようなことにはなりません。江戸時代には、わざわざハエトリグモを飼って、どちらが先にハエをつかまえるか競わせるゲームも一時流行していました。
■ユウレイグモ
体は1センチから1.5センチ程度ですが、足を開くと10センチ程度になるクモです。アメンボのように、足がとても細くて長いのが特徴です。物置や岩陰が好きで、家の中にいても色が薄いので見つけにくくなっています。コバエやチャタテムシなどの害虫を食べてくれます。
■ジョロウグモ
秋になると家の軒下や木の間などに蜘蛛の巣を張るクモです。体がカラフルでとても目立つので、一度は目にしたことがあるかもしれません。大きさは数ミリから3センチ程度になるクモで、本州や四国、九州地方などに生息しています。沖縄など南に行くと、より大きいオオジョロウグモが生息しています。
メスは胴体の部分が、黄色や赤、黒といった大変カラフルな模様をしており、足も黒と黄色のシマシマ模様のため、大変印象的なクモでもあります。毒はありますが、人間にとっては大変微量なので、咬まれたとしても害には及ばないケースがほとんどです。
■イエオニグモ
7月から11月に軒下でよく見かけるクモで、色はグレーや黒い色をしています。サイズは6ミリから12ミリ程度です。昼間は自分の作ったクモの巣をたたんで、夕方に巣を張り直します。
■オオヒメグモ
大きさは5ミリから8ミリほどで、色はグレー、黒、緑がかったものなどが見られます。一年中見られるクモで、不規則な形の巣を作ります。地面や壁を移動する昆虫を食べてくらしています。個体数が多く、巣の形もクシャクシャとした形で見苦しいので、巣を作ってほしくないクモの一つです。
■ヒラタグモ
名前のとおり平らなクモで、胴体は白の中に黒い模様があります。大きさは7ミリから9ミリほどで、足は太く短い形をしています。色としては目立ちますが、ずっと自分が張ったクモの巣の中にいるので、あまり外に出てくることはありません。雨が当たらない天井と壁の間などに、直径2センチから3センチほどのギザギザした形の巣を作ります。
■セアカゴケグモ 【危険】
セアカゴケグモは、全身が黒い色をしていて、名前の通り、背中に赤い模様がある大きさ1.5センチほどの小さなクモです。毒を持っている毒グモなので、気を付けましょう。主に生息しているのは、東南アジアやオーストラリアです。1995年に大阪で初めて発見され、マスコミでも話題になりました。
日本では大阪や兵庫を中心に、日本全国に生息地が広がっています。こちらから手を出さなければ、セアカゴケグモから咬んでくるようなことはありません。もしも咬まれると、大変痛く、咬まれた部分が腫れてしまいます。ひどい場合はめまいや吐き気が生じるケースもあります。公園のベンチの下などにいることがあります。
蜘蛛の生態

クモが嫌われる理由に、蜘蛛の巣があります。クモは、一度巣を壊されても、何度も何度も同じ場所に巣を作る習性があります。そのため、クモに巣をつくってほしくない場所に、前もって殺虫剤をスプレーしておくと寄り付かなくなります。
一般的なクモの巣の張り方ですが、最初は枝などにつかまりながら、お尻から何本もの糸を出します。何本かの糸のうち、どれかが物にくっつくと、その糸をつたって移動します。
糸を出しながら、元いた場所と糸がくっついた先を往復します。そして糸の中央部分まで来たら、下に降ります。下のほうにある草などに糸をくっつけて巣の外側の枠を作ったら、中央から外に向かって螺旋状に足場糸を張ります。枠と足場糸が張れたら、獲物をキャッチするための糸を丁寧に張っていきます。
薬剤を散布するのであれば、冬場よりも春から秋がオススメです。クモは1年から3年生き延びますが、冬は寒くて仮死状態になっているので、薬品を撒いてもあまり効果が無いのです。
■クモが好きな場所
クモが好きなのは『暖かい場所』『水に濡れない場所』『風が強くない場所』『静かな場所』
などです。また、クモは獲物がいる場所によく出現します。そのため、夜中でも照明がついていて、ユスリカや蛾が集まってくるような場所が大好きです。
屋外照明器具の周辺に蜘蛛の巣がよく張られますが、これは獲物がよく捕れるからなのです。
■クモの嫌いなニオイ、食材
クモが嫌いなニオイ
クモは柑橘系の香りやシダーウッド・バージニアの香り、バジル、レモングラス、ユーカリ、シトロネラ、シナモン、クローブなどの香りが苦手と言われています。
シダーウッドのアロマオイルには、シダーウッド・バージニアと、シダーウッド・アトラスがありますが、クモが苦手なのはシダーウッド・バージニアのほうです。バージニアはヒノキ科の木で、アトラスは松科の木から取れたオイルになっています。杉やモミの木の香りも苦手なので、杉やモミの木のウッドチップが販売されていたら、布などにくるんで家に置いておくと良いでしょう。
クモが嫌いな食材
クモはコーヒーがとても苦手です。クモがコーヒーを飲むと、カフェインによって神経が麻痺してしまい、でたらめな巣を作ってしまいます。テレビ番組で以前取り上げられたことから、話題になった時がありました。YouTubeにも画像がアップされているので、興味があったら見てみてくださいね。そのため、コーヒー豆をクモがよく出るところに撒いておくのもクモ予防になります。
蜘蛛を退治する殺虫剤5選

■1 アース製薬 クモの巣消滅ジェット
クモに直接スプレーすると一瞬で殺すことができ、家庭用クモ殺虫剤のエースと言って良い評判の殺虫剤です。業者に依頼する場合を除けば最強と言ってよいかもしれません。天井裏など、少し遠い所にスプレーしたい場合にも重宝します。
ただしジェット力が力強い分、無くなるのは早めです。多くのクモを退治する必要がある場合はまとめ買いがオススメです。
■2 フマキラー クモフマキラー
その場にいるクモだけでなく、待ち伏せ効果もあるスプレーなので、巣を作られて困る部分にスプレーしておくと良いでしょう。クモのタマゴにも、毒グモのセアカゴケグモにも効果のあるスプレーです。スプレー缶を逆さまにしても力強くスプレーできるので、縁の下など床下部分にも散布できます。
■3 KINCHO クモ用ハンター
クモの巣やクモの駆除用スプレーの中でも非常に人気のあるロングセラー商品です。殺虫剤としてクモに直接噴射して殺すほか、クモの巣を約一ヶ月ほど予防できます。即効性だけでなく、待ち伏せ機能もあるので、天井や床下などに散布しておくのがオススメです。
■4 プロ用 クモルスストレート プロケミ
殺虫剤ではなく、クモの巣を作らせないための薬品です。害虫駆除の専門家も使用しているスプレーで、こちらは200グラムですが、お徳用の1リットル入りのボトルもあります。水などで薄めずに、そのままスプレーして使用します。クモは嫌いだけれども、殺すのもイヤという方にオススメです。
■5 イカリ消毒 スーパークモジェット
クモに直接噴射して殺すこともできますし、巣を作らせたくない部分にもスプレーできるタイプです。スーパークモジェットの凄いところは、植木や盆栽など植物にも使用できる点です。植物から1メートルほど離して、1箇所につき1秒から2秒程度スプレーします。効果は1ヶ月程ありますが、雨が降った場合は再びスプレーしなおしてください。
蜘蛛を退治するグッズ3選

■1 くもの巣キャッチャー 電動式クモの巣クリーナー
一見、ただの棒に見えるので、ホウキや木の棒とどこが違うのかと感じるかもしれませんが、こちらは、スイッチを入れると先の部分が回転するので、クモの巣を巻き取ってくれる製品です。
棒を伸ばすと2メートル40センチになります。単2の乾電池を2個入れる電池式で、一度電池を入れると60分間持続します。
■2 TOWA クモの巣バスター
こちらも棒の先がブルブルと高速回転して、クモの巣を巻き取ります。連続使用は10分から20分可能で、単2の乾電池を2本使用します。長さが約2メートルまで伸びるので、高い所に作られたクモの巣も取ることができます。普段は77センチの長さの棒です。
■3 アズマ工業 ブラシ クモの巣取り
こちらは電動ではなく、器具の先のタワシのような部分に専用のシートをくっつけて、シートにクモの巣をからませるタイプの商品です。
ブラシの毛が大変良くできており、高い木の枝など取りにくい部分の巣もきちんと絡め取ってくれます。ブラシ部分の角度を、6段階に変えることができるので、照明器具の近くなど角度的に難しい場所にも対応できます。
使用後は、専用シートを捨てるだけ。ブラシ部分にはクモの巣はくっつきません。柄の部分は90センチから140センチに伸び縮みできます。5枚入りの専用取り替えシートも販売しています。
蜘蛛の駆除をプロに頼んだ場合の相場

プロにクモの駆除を頼んだ場合、10平方メートルあたり5,000円から10,000円が相場です。業者によっては、電話をしたら即日来てくれる場合もありますので気軽に電話してみましょう。
作業内容としては、蜘蛛の巣専用の殺虫剤を振りかけることが中心です。また、オプションで蜘蛛の巣がついてしまった照明器具の掃除をしてくれる場合もあります。業者に頼む時は、何をしてほしいのか電話で伝えてから見積もりをもらうようにしましょう。
業者によっては薬の散布が中心で、植木や壁、照明器具についた蜘蛛の巣を除去する作業はオプションの場合もあります。女性の一人暮らしなど、男性ではなく女性スタッフを希望する場合は、対応してくれるショップもあるのでリクエストしてみましょう。
業者には来てほしいけれども、ハシゴや道具で家財道具を破損されたりしないか心配な場合もあるでしょう。そのような場合は「損害保険」に加入している業者を選ぶと良いでしょう。その他、クレジットカードには対応しているのか、駐車場代は業者が支払うのか、こちらが支払うのかなど、気になる点は細かく質問をして納得した上で依頼するようにしてください。
蜘蛛は益虫

クモは、普段昆虫を食べて生きています。ゴキブリやネズミなどと違って、台所の食物を荒らすようなことはしません。それどころか、アシダカグモなどは家の中のゴキブリやハエといった害虫をつかまえて食べてくれるのです。また家の中の害虫だけでなく、畑の農作物につく害虫も食べてくれるので、農家では非常に重宝しているのです。
まとめ
クモのイメージは、あまり良いものではありません。全身が毛でおおわれた猛毒を持つタランチュラや、見た目の気持ち悪さから嫌われてしまいがちです。しかし、ハエやムカデ、ゴキブリなどと違って、クモは益虫であることも今回の調査でわかりました。
クモは益虫だから殺したくないけれど、クモの巣は家や庭に張ってほしくないという場合は、クモの巣を作られないスプレーを散布しておくと良いでしょう。