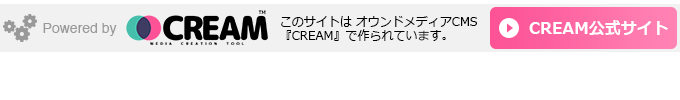栗を購入したり、拾ったりした際、食べる時に虫がいることに気付くケースは少なくありません。栗の中に虫がいると、食べたくなくなったり処分したりする人も多いでしょう。
結論からいうと虫食い栗かどうかを見分ける方法は以下の2つです。
- 穴が空いている場合はほぼ確実に虫食い栗
- 水に入れて浮いてくる栗は虫食いの可能性大
ちなみに栗に空いている穴は虫が侵入するために外から空けたものだけでなく、栗の中から虫が空けたものもあるんです!
本記事では
「なぜ栗の実の中から虫が穴を開けるのか?栗の中にいる虫の正体は?」
「虫食い栗の見分け方や虫食い栗の処理方法を知りたい」
「栗につく虫の発生を予防する方法はあるの?」
こんな疑問にお答えします!
本記事を最後まで読めば「栗を調理しようと思ったら虫が出てきた!」というショッキングな光景を再び目の当たりにすることもなくなるでしょう!
栗の中にいる虫の正体

栗の中にいる虫の種類は、基本的にクリジギゾウムシとクリミガと呼ばれる虫です。
クリシギゾウムシはゾウムシ類の虫であり、栗の中ににいる虫の80%はクリシギゾウムシだといわれており、幼虫は1週間程度で1cmの成虫になり、栗の実をエサにしています。
また、栗の皮に黒く小さな斑点が見られる場合は卵を産んだ跡であり、穴が空いていた場合は虫が外に出た跡です。高確率で卵を産み付けますが、孵化する前に剥いてしまえば栗の実だけは問題なく食べられます。
現在スーパーで売られている栗は、基本的に卵が孵化しないように処理しているため安心して食べられるでしょう。クリミガは、実に1つずつ卵を産み、孵化して栗の内部にまで侵入します。
栗の実をエサにして成長し、栗のイガに移動することが特徴です。幼虫は細長いですが、大きく生長して栗の殻を破るんで、大きな穴が空いてしまいます。
虫食い栗の見分け方・判別・選別方法

栗の皮に穴が空いていなくても、栗の中には虫がいる可能性があります。なぜなら栗につく虫は栗の花に卵を産み、虫の卵を巻き込んで栗の実が成長するからです。栗の実の穴は虫が外部から侵入したものではなく、栗の実を食べた虫が成長し外に出たあとということ。
そのため栗を購入したり拾ったりした際に「穴が空いていない栗だ」と安心していても、虫食いの栗にあたることがあります。なお1つの栗に数匹の虫がいるケースもあるため、穴が空いていたとしても中にまだ虫がいるかもしれません。
虫食い栗の判別方法は以下のカテゴリにまとめているので参考にしてください。
栗の中の虫を出す方法・処理方法は?食べられる?

虫食いの栗は、処理すれば食べることが可能です。ただし、食べられない箇所もあるため、見分ける方法についても確認しておきましょう。
【基本的な処理方法】
容器や鍋に水と栗を入れて、半日程度時間をおきます。水を切って新聞紙に広げ、日陰で乾燥させましょう。万が一虫がいた場合、水に入れた段階で絶命します。
【卵を処理する方法】
卵があっても孵化させないうえに、虫も取り除くためには、熱湯を使う方法が有効です。80度のお湯に栗を入れ、2分程度温めます。温めたら新聞紙のうえに広げて、日陰で干して乾かしましょう。卵も成虫も同時に処理できます。
【食べられる部分の見分け方】
栗の実が茶色い場合には食べることが可能です。ただし、栗本来の色ではなく、虫がいた周辺が茶色く変色している場合には注意しましょう。
【食べられない部分の見分け方】
栗の実が黒く変色している場合、傷んでいるため食べないようにしましょう。また、栗の皮が腐り、柔らかくなっているものも避ける必要があります。
黒くなる原因は、栗を拾った日、もしくは購入した日から日数が経って劣化した可能性が高いです。拾ったり購入したりした日から長期間保存せず食べる、もしくは正しい方法で保存する必要があります。
虫食い栗の見分け方から調理におすすめアイテム ■虫食い栗を見分ける→調理までこれ1つ!

GREENPAN/グリーンパン
\リニューアル/フェザーウェイト ココットラウンド(両手鍋) IH対応 22CM ポットホルダー2個付
栗が入る大きなお鍋が無いという方でも大丈夫!大きめ両手鍋ならたっぷりの栗を水に浸せます。
「栗を水につける→煮る→栗ご飯を炊く」という調理までこれ1つで完成!フタの構造が素材のうま味を含んだ水蒸気を循環させるので、いつもの栗ご飯がもっと美味しく炊き上がります。
栗の実を虫から守る予防対策5個

購入した栗や拾った栗を虫から守るためには、どのような方法があるのでしょうか。
そもそも栗の実を虫から守るためには、栽培段階で花についた虫の卵を除去する必要があります。つまり、購入したり拾ったりした栗を「虫から守る」ことは難しいため、「虫食いの栗を食べてしまうといったトラブルを予防する」ことが重要です。
正しい方法で保存し、虫の大量発生や虫の影響で栗の実が劣化しないように工夫しましょう。そこで、自宅でできる予防方法(保存方法)を5つ紹介します。
【皮付きの栗を虫から守る予防対策】
大きな容器に水を張り、栗を水に入れた状態で保存すると1週間程度常温のままで保存できます。ただし、毎日水を替えましょう。水に入れることで虫が死滅し、虫が居る栗は浮くので簡単に判別できることがメリットです。
【むき栗を虫から守る予防対策】
むき栗は傷みやすいため、可能な限り早めに食べきることが大切です。しっかり洗い、氷水の中に入れて冷蔵保存すれば3日程度保存できます。冷凍処理する場合は、水で洗い、茹でて冷凍庫で保存します。解凍する際には、お湯に入れて煮てから食べましょう。
【冷蔵保存で虫から守る予防対策】
栗をしっかり洗い、水気を切ったら新聞紙で包んで冷蔵庫に入れます。栗の種類によって異なりますが、3日~1週間程度で食べきるようにしましょう。
水に入れても虫が死滅していなかった場合、被害が拡大するため注意しなければなりません。また、冷蔵庫に入れていると、栗の中にいた虫が出てくることがあります。そのため、新聞紙で包み、ビニール袋に入れる方法が有効です。
【冷凍保存で虫から守る予防対策①】
皮つきの生栗は、1日天日干しをして栗の糖化を進めて甘さを引き出しましょう。天日干しをする前に栗を洗わず、表面の汚れを適度に落とします。
天日干しをしてから新聞紙で包み、密閉容器や袋に入れて冷凍庫に入れれば虫の被害を予防することが可能です。半年程度保存できるため、食べる分だけスムーズに取り出せるように小分けにすると良いでしょう。
凍った栗をそのまま熱湯で茹でれば、茹で栗として食べられます。5分程度熱湯に入れて回答すると、皮も渋皮も柔らかくなるためスムーズに皮を剥けるでしょう。
【冷凍保存で虫から守る予防対策②】
下茹でをすればより甘さを引き立てることが可能です。容器に水を張り、1時間程度栗を浸けて虫を死滅させます。確実に虫を取り除きたい場合には、半日ほど水に浸けておくと安心です。
次に、栗を鍋に入れ、栗が浸る程度の水を入れて中火にかけます。沸騰する直前で弱火に変えて、1時間程度茹でましょう。弱火で時間をかけて茹でると、栗の甘さが増します。
お湯が減ったら注ぎ足し、アクを取ることも大切です。1時間茹でたらザルにあげて熱をとり、水分を拭き取ります。冷凍しないでそのまま使用する場合には茹でた汁ごと冷ましましょう。
3時間程度時間をおけば十分です。冷凍保存する場合、栗が重ならないように袋や容器に並べて入れ、冷凍庫に入れれば3ヶ月程度保存できます。
まとめ
栗に発生する虫は、外部から侵入するケースは少なく、栗の中で生長した虫が外に出たり、成長段階で栗の中に潜んでいたりすることが一般的です。
自宅で栗を食べる際には、水やお湯を使って虫食いの栗を判別し、虫を死滅させたうえで安心して食べられる栗を保存する必要があります。ただし、むき栗は長期間保存できないため、3日程度で食べきることが理想です。
結露が発生しないように口を開けた状態のビニール袋に入れ、冷蔵庫で保管するのもよいでしょう。冷蔵庫で保管している際にも、栗が乾燥した状態を維持できるように混ぜることがポイントです。
虫食い栗を見分けたうえで、食べられる部分と食べられない部分を判断し、おいしく食べられる部分まで処分しないようにしましょう。