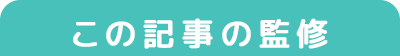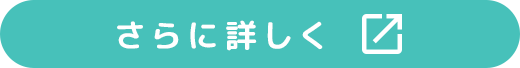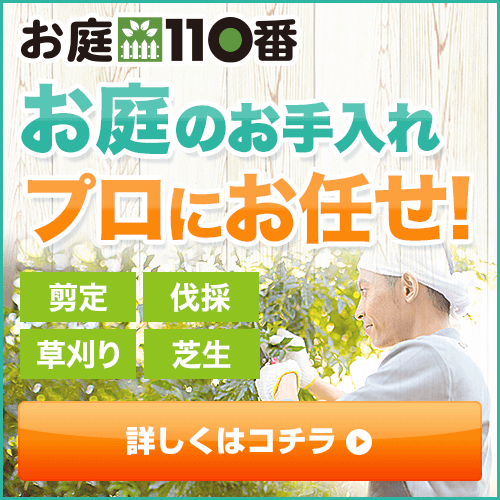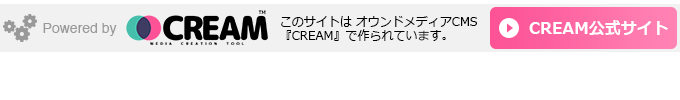雑草は、一体何種類くらいあるのでしょうか?むしっても次々と生えてくる雑草取りに、うんざりしている方も多いでしょう。庭や畑を覆い尽くしてしまう雑草は、本当にやっかいな存在です。
雑草を効果的な除草をするには、まず敵を知ることが第一です。ここでは、雑草を科ごとに10種類に分け、それぞれの特徴について調べてみました。
雑草の種類10パターンと見分け方

雑草は大きく分けると「1年草」と「多年草」に区別することができます。
■1年草
1年草は、春もしくは秋に新芽が出ます。春に新芽が出たものは冬に枯れますが、秋に新芽が出たものは冬を越して夏に枯れます。越冬する雑草は強いものが多いので、液体タイプの除草剤で駆除した後引き抜き、土だけになった場所に粒タイプの除草剤を撒くと良いでしょう。
ただし、現在は多くの除草剤が出ていますので、取り扱い説明をよく確認し用途に合わせて適切に使用してください。
■多年草
多年草は、冬に枯れるので一年草と勘違いしがちですが、地下茎がエネルギーを蓄えながら生き残っています。そして、春になると地下茎から新芽を出して成長します。地面の下の地下茎で増えるので、除草剤を使わない場合は地面を掘らないと駆除が困難な雑草です。駆除には手軽な液体タイプの除草剤がオススメです。
粒状、液体タイプでもやはり取扱説明をよく確認し、それぞれの用途に適した使用方法で行ってください。
1 イネ科
エノコログサ(ネコジャラシ)
エノコログサは形が犬の尻尾に似ているので(犬っころ草)と呼ばれていましたが、次第にエノコログサという名前になりました。今では犬ではなくて「ネコジャラシ」という俗称で呼ばれることが多い雑草ですよね。日当たりの良い庭や荒れ地によく見かけられます。
粟(アワ)の原種とも言われており、食用としては流通していませんが食べることもできます。除草剤としては防除の難しい雑草も駆除してくれる「アージラン」がオススメです。
チガヤ
イネ科の雑草である「チガヤ」は、夏にはると葉の先端が赤くなるのが特徴です。北海道から沖縄まで日本全国で見ることができ、春から初夏にかけて暖かくなると白い穂をつけ、種は風にのってよく飛びます。そのため、除草は穂をつける春よりも前に行わなくてはいけません。粒タイプの除草剤を、寒い時期から土に撒いておくと良いでしょう。
メヒシバ
メヒシバは一年草で、日本全国に見らえっる雑草です。春から秋にかけて見られる雑草で、種で繁殖します。高さは10センチ程度のものから80センチくらいにまで成長し、葉は細長い形をしています。夏に小さな穂を出して、その中に種ができます。除草は、種ができる前、春までに行いましょう。
オオバコ
オオバコはイネ科の多年草で、葉っぱが大きいので(大きな葉の子)「オオバコ」と呼ばれています。摘み取られても踏まれても成長し、日本では北海道から沖縄まで見ることができます。葉や種は咳止めになり、元気がなくなったカエルをオオバコの下に置いておくと元気になるという言い伝えもあります。
種は車前子(しゃぜんし)という漢方薬になり、利尿作用や咳止めに使われます。根は地下深くにまで張っているので、上だけ摘み取ってもすぐに再生してしまいます。液体タイプの除草剤がオススメです。
カモガヤ
英語名ではオーチャードグラスと呼ばれている雑草で、牛などの家畜に食べさせる牧草として世界的に知られています。寒さにも強く、春に花が咲きますが春の花粉症の原因の一つにもなっています。スギ花粉の後に花粉が飛ぶので、寒い時期に液体タイプの除草剤で駆除しましょう。
ススキ
秋の七草の一つでもあるススキは、秋の花粉症のアレルゲンの一つでもあります。日本全国どこにでも生息していて、日当たりの良い場所に生えることが多い植物です。背の高いものになると2メートル程度の高さになり、秋には花穂から種子を飛ばします。葉を触ると手を怪我することがあるため、子どもがいる家庭では気をつけましょう。
2 キク科
オオアレチノギク
秋になると土から顔を出し、冬には枯れずに持ちこたえた後、夏に2メートル近くまで伸びる雑草です。葉にはうぶ毛が生えていて、白い花が咲きます。海外から来た外来種で、本州から九州まで分布しており、農地によく生えるため問題になります。要注意外来生物にも指定されているので、農作物のためにも見つけたらすぐに駆除することをオススメします。
ブタクサ
秋の花粉症で知られる雑草です。黄色い花が咲き、大きくなると1メートルほどに成長します。元は北アメリカ原産で、日本には明治期に入ってきました。7月から10月にかけて花が咲くため、それよりも前の除草が効果的です。
ヨモギ
草餅にしたり、天ぷらにしたりと食用によく使われる植物です。ヨモギの葉の産毛は、集められてお灸の時に使うモグサになります。非常に利用価値の高い植物ですが、繁殖力があるため雑草として見ると厄介な植物です。ブタクサのように秋の花粉症の原因の一つでもあるので、イネ科と広葉雑草に強い除草剤「ザイトロン」を使うと良いでしょう。
タンポポ
子供の頃に種を飛ばして遊んだタンポポも、雑草として見ると根が深くまであるので駆除しにくいものです。昔から日本で育っている種類のタンポポと、海外からの外来種のタンポポがありますが、外来種のほうが繁殖力が強い性質があります。寒さにも強いので、液体タイプの除草剤を塗って、根まで枯らしましょう。
3 ナデシコ科
ハコベ(ハコベラ)
春の七草の一つでもあるハコベは、よく枝分かれしてあちこちに密集して花を咲かせます。ハコベは世界に120種もの種類があり、日本ではその中で18種類生息しています。高さは高いもので50センチ程度になりますが、大抵地面を這うように20センチ程度の高さのものがよく見られます。春から秋までほぼ一年中花を咲かせ、冬にも強い雑草なので枯れることはありません。
液体タイプの除草剤で駆除すると良いでしょう。
ツメクサ
葉っぱが鳥の爪に似ているので「ツメクサ」という名前がついたと言われている植物です。北海道から九州にかけてよく見られ、地面を這うようにして広がります。道端のコンクリートの間などによく見られる丈夫な植物で、花が4月から7月の間に咲きます。
4 カヤツリグサ科
ハマスゲ
春から秋にかけて見られる雑草で、種でも増えますし、地下茎でも増える雑草です。砂浜や芝生、畑や道など、どんな条件下でも生えるため、多少刈った程度では、すぐに再生してしまいます。じょうぶな地下茎を伸ばして繁殖するため、液体タイプの除草剤で駆除しましょう。
ヒメクグ
漢字で「姫莎草」(ヒメクグ)と書く多年草で、茎を両端から割くと四角形の蚊帳に似た形になります。30センチ程度になる雑草で湿った日向を好むため、田んぼのあぜ道によく生えています。成長すると、茎の先に1センチ程度の丸い穂をつけます。見た目は可愛い植物ですが、爆発的に増えるので厄介な雑草です。
5 トクサ科
スギナ
スギナは浅い地面でもよく繁殖するため、しつこい雑草として知られていますが、春になると地下茎からツクシが生えてきます。茎をスギナ、胞子茎をツクシと呼んでいて、ツクシの方は春の山菜として食べられます。また、ツクシのエキスが花粉症対策に役立つ可能性があり、日本大学産官学連携知財センターなどで研究がすすめられています。
6 トウダイグサ科
トウダイグサ
トウダイグサ(灯台草)は日当たりの良い土地に生えており、毒を持つ雑草として知られています。そのため、子どもやペットがいる家庭では、見つけたら早い時期に駆除してください。30センチくらいまで伸び、本州や九州で見られます。
また、4月から6月にかけて黄色い花が咲きますが、毒がありますので子どもがままごと遊びなどで触れてしまわないように気をつけてください。
7 シソ科
ホトケノザ
成長すると30センチ程度の高さになり、3月から6月にかけて花が咲きます。花びらを取って吸うと蜜が甘いので、子どもがそれで遊ぶこともあります。本来、ホトケノザは食用ではありません。コオニタビラコという植物が、名前をホトケノザと勘違いされて春の七草になっています。
こちらのホトケノザは食べられませんので、気をつけてください。
8 ゴマノハグサ科
オオイヌノフグリ
畑や道端でよく見られる雑草で、「大犬の陰嚢」というちょっと変わった名前が印象的です。秋に芽を出した後に冬を越し、春にコバルトブルーの花が咲くので可愛らしい草です。1つのオオイヌノフグリから500個以上の種ができることもあり、非常に繁殖力の高い雑草です。日本には明治時代に外国から入って来ましたが、世界中で繁殖している雑草です。
9 カタバミ科
カタバミ
クローバー、シロツメクサなどとよく間違えられる雑草です。種や、地面に這うようにして増える茎から増えます。クローバーは葉に白い線状の模様がありますが、カタバミには白い線はありません。春から秋にかけて5弁の黄色い花を咲かせます。
種ができると、周囲1メートルの距離まで自分の力で勢い良く弾き飛ばします。一年を通じて成長する雑草なので、花が咲いて種ができる前に除草してください。
10 マメ科
ヤハズエンドウ(カラスノエンドウ)
3月から6月にかけて、エンドウに似たピンク色の花が咲きます。本州から九州、沖縄まで生えており、秋に芽が出て有るに高さ1メートル以上にも成長します。天ぷらなどにして食べることもできますが、食用としては流通していません。種ができると晴れた日に遠くまで種子を飛ばすので、放置しておくと一帯に繁殖してしまう雑草です。
雑草の駆除対策方法
■除草剤
除草剤は『粒タイプ』『液体タイプ』の2種類あります。粒タイプは時間をかけて、じっくり効果があらわれるものです。そのため、雑草を生やさないようにする時に使うと良いでしょう。まだ寒い時期で雑草が出る前の土に、粒タイプの除草剤を撒いておくと良いでしょう。粒タイプの除草剤は、もう生えてしまった雑草には効かないので注意しましょう。
除草剤の液体タイプは、もう既に生えてしまった雑草を枯らすための薬品です。液体タイプの除草剤は、葉に薬品が触れることで根まで除草剤が染み渡り、最後には雑草を丸ごと枯らすという仕組みです。効果が早いものになると次の日には雑草が茶色く枯れているので、今すぐ何とかしたい場合は液体タイプです。
また、カマや草取りなどを使って根ごと引き抜くのもいいと思います。カマにも様々な種類がありますので試してみるものいいでしょう。
■防草シート
雑草が生えないために、砂利を庭に撒いている家庭も多く見られます。しかし、砂利の間から雑草が出て来るようになると、雑草抜き作業をしなくてはいけません。
砂利の下に防草シートを敷いておけば、面倒な雑草抜きもしなくて済みますし、玉砂利や化粧砂利が綺麗に見えます。また、砂利を敷いていない場所でも、防草シートを地面の上に敷くだけで雑草とサヨナラできるのです。
雑草シートはホームセンターや園芸店などで、メートル単位で売られています。地面にシートを敷いて、15センチ程度のUの字型の固定ピンで地面に固定するだけなので、初心者でも簡単にできます。
1平方メートルにつき200円程度のものから、400円程度のものまで値段に開きがありますが、高いものほど長期的に雑草が生えなくなりますし、持ちも良いです。安いお手軽タイプの黒い織布防草シートは、目が荒くすぐに雑草が生えてきてしまいます。ずっと太陽の光に当たるものなので、防草シートは紫外線でダメージを受けやすいのです。
ブルーシートは水が浸透しないので、水は通さないため上に水たまりができてしまいます。その点防草シートは、雨水を地面まで通してくれるので雨上がりに水たまりで困ることもありません。
当社でお勧めするのはデュポン社のザバーンです。透水性で耐久性も抜群でメーカーでは10年の耐久性を示しております。また施工しやすいのも特徴です。
本文でもあるように、シートを敷いた上に玉砂利など敷くときれいに仕上がります。
まとめ
雑草には様々な種類がありますが、大きく分けて「一年草」と「多年草」があることがわかりました。また、春に芽が出る雑草もあれば、秋に芽が出る雑草もあり、秋に芽が出る雑草は寒い冬を越えるので耐寒性が非常に強いこともわかりました。
もし、家の庭に生えている雑草のどれか一つが花粉症の原因だとしたら、その種類の雑草を除草するだけで症状が軽くなるかもしれません。冬に強い雑草は、いつまでも枯れることが無いので、葉が出ているうちに液体タイプの除草剤で駆除する必要があります。
冬に枯れる一年草が生える場所には、粒タイプの除草剤を撒いて、春になったら雑草が芽を出さないようにしましょう。