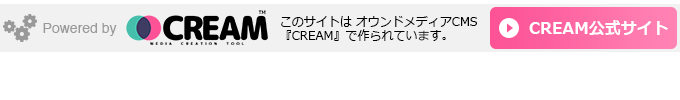しいたけは1年に2回旬があり、3月~5月、9月~11月は最も美味しいと言われています。特に天然もののしいたけはうま味と風味が最高です。しいたけの旬になると、知人などからもらう方もいるのではないでしょうか?
一方でしいたけは虫が付きやすいことで知られています。虫は大量発生することもあり、かなり気色悪い光景を見ることになるかもしれません。例えば、”保存していた生しいたけを数日ぶりに見たら虫が湧いていた”、”農家さんで買ったしいたけに白い虫が付いていた”などの話はよくあります。
しいたけに虫が付いた時は3つの方法で対処しましょう。しいたけに付く虫の種類、食べない方がいいしいたけの特徴などもご紹介していきます。
スーパーのしいたけは洗うよりふきとりがおすすめ

あなたはしいたけを洗ってから調理をしますか?結論から言うと、しいたけは虫が付いていなければ、洗う必要はなく拭き取るだけかまいません。しいたけを水洗いすると、うま味、風味、栄養分が流れてしまいます。
しいたけの栽培方法は、『原木栽培』と『菌床栽培』の2通りあり、スーパーで流通しているのは主に菌床栽培のものです。
菌床栽培のしいたけは、温度や湿度管理されている工場で栽培されており、良好な衛生環境で栽培しています。工場生産のしいたけは虫の付着率が低く、農薬も使用していないため拭き取るだけで問題ありません。
【しいたけを拭き取る方法】
水を含ませて固く絞ったキッチンペーパーで、しいたけのヒダや裏側を軽く拭き取りましょう。キッチンペーパーを強く押し付けて拭き取る必要はありません。また、しいたけは水分を吸収しやすく、キッチンペーパーの水分が多いと水っぽくなるためよく絞りましょう。
しいたけにつく虫の種類

食材に虫が付いていると、不快に感じる方も多いのではないでしょうか?”もらったしいたけに白い虫がウジャウジャ付いていた”など、しいたけと虫に関する話は珍しくありません。
しいたけに付いている虫は裏側やヒダに身を潜めていることが多いです。なお、しいたけは様々な種類いの虫が付きますが、今回は定番の虫3種類を以下にまとめました。
【1.】トビムシ
トビムシはかなり小さい虫で見た目は細長くて黒いです。しいたけのヒダの隙間にビッシリいることもあり、よく観察しないと何かのカスと間違えるかもしれません。
【2.】ショウジョウバエ
ショウジョウバエは腐った果物を好む虫ですが、しいたけなどのキノコ類にもよく付いています。なお、幼虫は白い虫でウジ虫と間違える方もいるでしょう。
【3.】キノコバエ
キノコバエもしいたけなどを含むキノコに付きやすく、茎の栄養を吸い取る虫です。見た目は白や半透明で、腐敗している植物の周り、薄暗くて湿気が多い場所を好みます。
しいたけのひだ・裏側には虫がつきやすい

”原木しいたけを食べてみたい”、”栽培キットでしいたけを育ててみたい”という方もいるでしょう。しかし、原木栽培や栽培キットのしいたけは虫が付きやすく、ヒダや裏側に密集していることがあります。原木栽培、栽培キット、ヒダや裏側に虫が付きやすい理由を以下にまとめました。
【1.】原木は自然栽培のため虫が付きやすい
原木栽培のしいたけに虫が付きやすい理由は、自生しているしいたけと同じ環境で育てているからです。原木にしいたけの菌を植え付けて、山中で約半年~2年かけて栽培します。自然の中で栽培するため必然的に様々な虫が付きやすいです。
【2.】栽培キットは置く場所によっては虫が付く
基本的に栽培キットは虫が付きにくく、室内でしいたけ栽培できることから人気があります。ただし、自宅は工場と違い、虫が侵入する可能性が高く虫が付きやすいです。特に屋外に置いて栽培すると、虫が付きやすいため注意しないといけません。
【3.】しいたけのヒダや裏側は虫が好む環境
しいたけに付く虫の多くは、湿気があり日陰の場所を好む種類がほとんどです。しいたけのヒダや裏側は、日陰になるため虫が付きやすい条件が揃っています。
しいたけにつく虫の取り方・だし方
しいたけに付いている虫を取り出す方法を以下にまとめました。虫に直接触れたくない方はピンセットなどを使いましょう。また、ピンセットはヒダの隙間にいる虫や、小さな虫も取りやすいため便利です。
■塩水につける

しいたけに付いている虫は、塩水につけると死滅させることができます。『虫だし』と呼ばれている定番の方法で、ヒダにあるゴミも落とすことが可能です。ただし、しいたけを塩水につけると傷みやすくなるため、早めに調理するか干して乾燥しいたけにしましょう。
【塩水につける方法】
1.)ボウルなどの容器に水と塩を入れます。分量の目安は、1Lの水に対して塩は大さじ1杯~2杯です。
↓
2.)塩水の中に虫が付いたしいたけを入れて約10分~15分待ちます。虫を塩水に漬けて死滅させるため完全に浸すのがポイントです。しいたけのかさを下にして、ヒダや裏側が上を向いている状態で浸します。時間が経ったら死滅した虫を取り除きましょう。
■密閉袋に保存する

密閉袋で虫を排除するメリットは、水を使わないためしいたけが傷みにくいことです。ただし、密閉袋の中の空気がなくなるまでは時間がかかり、すぐにしいたけを使いたい時は向いていません。
【密閉袋で保存する方法】
1.)虫が付いているしいたけを密閉袋に入れてしっかり封をします。1日程度待って虫を窒息死させましょう。
↓
2.)ほとんどの場合、1日程度経つと虫は窒息ししています。絶対に動いている虫を見たくない方は、1日半程度待ってから封を開けて虫を取り除いてもいいでしょう。
■冷凍保存する

しいたけに付いている虫は冷凍保存して死滅させることもできます。ただし、凍った虫はしいたけに付いていることがあり、取り除く作業は時間がかかるかもしれません。
【冷凍保存の方法】
1.)しいたけを保存袋に入れたら冷凍庫で凍死させます。しいたけは完全に凍らせてもいいですが、虫が動いていなければ半冷凍でもかまいません。
なお、半冷凍の方が虫を取やすいです。しいたけを完全に冷凍すると、氷に虫がくっ付いて取りにくくなることがあります。
↓
2.)しいたけに付いている虫が動かないしことを確認して、ピンセットなどで取り除きましょう。必ず半冷凍や完全に凍っている状態で虫を取ってください(水っぽくなり味や風味が落ちるため)。
しいたけに付いた虫は食べても大丈夫?

”虫が付いている野菜は栄養がある証拠”と、聞いたことがありませんか?確かに虫が付いているしいたけは栄養価が高いですが、虫と一緒に食べても大丈夫なのか不安になる方もいるでしょう。
万が一、しいたけに付いている虫を一緒に食べたとしても問題はありません。ただし、キノコバエやショウジョウバエの幼虫など一部の虫に限ります。理由は、キノコバエやショウジョウバエの幼虫などは、人体に有害となる物質や分泌液を出すことはないからです。
とは言え、虫が付いているしいたけを食べるのは抵抗がある方も多いでしょう。しいたけに付いている虫は取り除いてから調理するのが基本です。しいたけを塩水に漬けるなどして、虫を死滅させてから調理して食べましょう。
食べない方が良いしいたけの特徴

しいたけは乾燥させて長期保存することができる便利な野菜ですが、食べない方がいいしいたけもあります。食べない方がいいしいたけは、うま味、風味、食感などが落ちているため美味しくありません。また、人体に悪影響を及ぼすこともあるため注意が必要です。
■ナメクジがついたしいたけ
ナメクジが付いているしいたけは、脳や脊髄に影響を及ぼす恐れがあることから食べることをおすすめしません。
ナメクジは寄生虫(広東住血線虫)と共存している場合があり、口にする脳や脊髄が炎症を起こすリスクがあるからです。また、しいたけを見た時にナメクジがいなくても、しいたけを這った時点で寄生虫が付いている可能性があります。
ナメクジそのものは悪い虫ではありませんが、寄生虫を持っているナメクジは危険です。しいたけにナメクジを見つけた時はもちろん、しいたけにナメクジが這った跡があれば食べるのはやめましょう。
■虫食い・傷んだしいたけ
虫食いがあるしいたけ、傷んでいるしいたけも食べない方がいいです。口にすると食中毒になる恐れがあり、激しい嘔吐や下痢などを引き起こすかもしれません。
虫食いがあるしいたけは、すでに傷んでおり腐敗が進行していると思いましょう。腐敗したしいたけは刺激臭があり、臭いにつられて虫が集まってきます。また、変色、ヌメリ、水分が出て水っぽくなる、味が不味いなどの特徴もあるためすぐにわかるでしょう。
まとめ
菌床栽培のしいたけは虫が付いている可能性はほぼありませんが、原木栽培や栽培キットのしいたけは要注意です。保管する際や調理をする前に、しいたけの裏側やヒダを見て虫がいないか確認してください。しいたけに虫が付いている時は、塩水に漬けるなどして処理をしてから食べましょう。