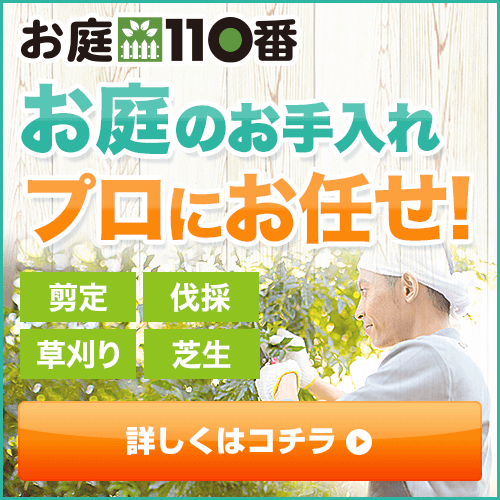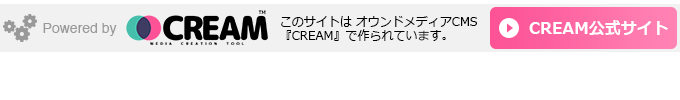お庭のアクセントとして木を植えたり、柿の木などの果樹を植えたりしている家も多くあります。
それらの木は、見栄えも良く季節ごとに果物が食べれるなど、四季を感じ暮らしに彩りを与えてくれる存在です。
ですが大きくなりすぎて隣の家にはみ出しそうになったり、引っ越しなどで庭木を処分せざるを得ない場合も。
本記事では、そんな困った事態に自分でもできる「木を枯らす方法」3つを紹介します。
また「根まで枯らす方法」「やってはいけない木を枯らす方法」なども併せて解説。自分でできない場合の業者での費用相場もお伝えするのでチェックしてくださいね。
木を枯らす方法①木の表皮を剥ぐ
木を枯らす方法1つ目は木の表皮を剥ぐ方法です。幹の表面の皮を1枚剥いで、木を倒すことなく枯らすことができる方法。
木は、根から吸い上げた栄養や水分を表面の皮を通して枝や葉に取り込んでいきます。そして葉の光合成によって作られた栄養が再び表皮を通って根に戻り、しっかりとした根を張るのです。
そのため表皮を剥いだりロープで縛ると、木が育ち生きるための循環が絶たれます。その結果、木が枯れるというわけなのです。この方法は巻き枯らしと呼ばれています。
【表皮を剥ぐ】巻き枯らし方法の手順 ■1cmの深さまで切り込みを入れるのがポイント!
皮を剥いで木を枯らす方法です。必要な道具と手順を紹介します。
・のこぎり(チェーンソー)
・ハンマー
・マイナスドライバー
次に手順を解説します。
①のこぎり(チェーンソー)で1cmほどの深さの切れ込みを幹1周分入れる
②20~30cm下にもう1本①と同じような切れ込みを入れる
③切り込みを入れた①と②の間に縦向きに切り込みを入れる
④切り込みからマイナスドライバーを差し込む
⑤ハンマーでドライバーをたたいて表皮を剥いでいく
しっかり1cmほどの深さまで切り込みを入れましょう。浅すぎると養分の通り道が破断されません。切り込みを入れることができたら、あとは比較的楽に皮をはいでいくことができます。
枯れるまでの期間は、約半年~1年ほどです。
木を枯らす方法②幹をロープで縛る
木を枯らす方法2つ目は、幹をロープで縛る方法です。
成長する過程で、ロープが幹に食い込んでいき栄養や水分が破断されます。その結果枯れるという仕組み。こちらの方法も巻き枯らしと呼ばれます。
【ロープで縛る】巻き枯らし方法の手順 ■コツはロープできつく縛ること
ロープを幹に巻いて木を枯らす方法です。道具と手順を紹介します。
・丈夫なポリエチレン素材のロープ
・軍手や滑り止め付きのグローブ
必要なものはロープと軍手の2つだけです。手順についても簡単。
①ポリエチレンロープを幹に数回巻き付ける
②きつく縛る
養分が破断されるようにきつく縛りましょう。ロープを使う方法では、木が枯れるまで2年ほどかかる場合があります。

SOOMLOOM
ガイロープ テント用ロープ 2mm 3mm 4mm 反射材付き
アウトドア用に作られた耐荷重340kgの頑丈なロープ!しっっかりと力を入れて木に巻きつけることができます。
全天候型で雨・風にも強いため、木に巻きつけたあと天気を気にしなくて良いのも嬉しいですよね。

薄手フィットすべり止め付き 手袋 軍手 滑り止め
しっかりと木にロープを巻き付けるためにはホールド力のある軍手が必須。こちらの軍手はバツグンのホールド力で、日々物を運んだりといった軽作業をしている方から人気のアイテムです。
手にピッタリとフィットするので、木にロープを巻くときも滑り知らずでギュギュと巻きつけることができるでしょう。
木を枯らす方法③除草剤や灯油を使う
木を枯らす方法3つ目は、除草剤や灯油を使う方法。幹に除草剤や灯油を流し込んで枯らします。
除草剤には、光合成を邪魔したり成長に必要な成分の生成を妨げるなどの作用があります。その作用で木を枯らすのです。
また灯油は除草剤よりも弱めですが、幹の中の水分を一緒に蒸発させて枯らす効果が。手順や注意点を解説しますね。
除草剤や灯油を使った手順 ■ドリルの穴は中心に向かって斜めに開ける
除草剤や灯油を使って木を枯らす方法です。準備物から紹介します。
・グリホサート配合の除草剤もしくは灯油
・電動ドリル
・スポイトやロート(じょうご)
・ビニールテープやラップ
これらの道具が準備できたら、下記の手順でやってみましょう。
①ドリルを使って幹に数か所穴を開ける
②スポイトやロートで除草剤もしくは灯油を流し込む
③雨水などが入り込まないようビニールテープやラップで穴を覆う
除草剤や灯油が流れ出ないよう斜め下に穴を開けるのがポイントです。
除草剤は、成分にグリホサートが配合されているタイプがおすすめ。内部にしっかり浸透して木を枯らします。
また枯れるまでの期間は、除草剤の場合、雑草ならスムーズに進めば1か月程度で枯れますが、木は1年ほどかかると考えておきましょう。
灯油の場合は、除草剤よりも効果が弱いため、①~③の工程を数回繰り返す必要があります。
木を枯らすおすすめの除草剤 薄めて使うタイプ!雨にも低温にも強い

日産化学
ラウンドアップマックスロード 1L
雑草の処理でも定評のあるラウンドアップマックスロードは、グリホサート系の除草剤です。
木も枯らすことができます。また、散布・塗布後1時間が経過すれば、雨が降っても大丈夫です。さらに気温が低い場合も効果があります。
雨や低温といった過酷な状況でも枯殺率は95%をキープ。
土に落ちてしまっても、土壌にいる微生物によって分解されるので、塗布・散布後でも種をまいたり植え付けができます。
木を枯らす方法を行うときの注意点
木を枯らす方法を試すときに注意しておきたいことです。
・時季に気を付ける
・巻き枯らしに向かない木がある
・取り扱いに注意する
・除草剤や灯油の使用を知らせる
巻き枯らしは、4月~8月の春夏にかけて行うのが望ましいでしょう。寒い季節よりも表皮に水分を多く含んでいるため剥がしやすいのが理由です。
また、アカシアの木や杉の木などの常に葉が茂っている常緑樹は、新芽が出やすく枯れにくい特徴があります。
そのため、ある時期になると葉が落ちる落葉樹と比べてもっと多くの時間がかかる場合も。枯らしたい木の種類もチェックしておきましょう。
それから、除草剤や灯油は、子どもやペットの手が触れないように管理しておくことが大切です。
また木に薬剤を使う際は、どの木に使用しているかが分かる状態にしましょう。近づかないように周りに張り紙やロープを張ったり、周りを柵で囲んでおくのもひとつの手です。
どちらも立木のまま枯れていきますが、幹の中が乾燥するともろくなります。倒れる可能性もあるので、周りに建物や人が集まる場所がないかも確認しておいてくださいね。
枯れた木の見分け方
巻き枯らしや除草剤などを使った木を枯らす方法は、半年~2年ほどの年月をかけて立木のまま徐々に木を枯らしていきます。
そのため見た目にはなかなか枯れたかどうかの判断がしにくいことも。そこで木が完全に枯れたかどうかの見分け方も紹介します。
・枝を曲げるとパキっと折れる
・幹を削ると茶色
木が枯れたかどうかを判断するには、この2つをチェックしてみてください。
水分がなくパサパサした木は枝がパキっと折れてしまいます。また、元気な木の幹を削ると緑色なのに対し、完全に枯れてしまった木は茶色になっているのです。
このような状態になっていれば、伐採や伐根をするといいでしょう。
木を枯らした後は根を枯らす!3つの方法
木を枯らす方法を行った後、伐採をしましょう。そして伐採が終われば、根まで枯らすことをおすすめします。
なぜなら木の処分は、害虫の住処とならないよう最終的に根を引き抜くところまで。そのため根を枯らしておくことで、水分が抜け軽くなり作業が楽になるのです。
ここでは、根を枯らす3つの方法を紹介するので、試してみましょう。
伐採後の根を枯らす方法その1 ■除草剤を使う
1つ目の方法は、除草剤を使います。木を枯らす方法でも紹介しましたが、除草剤は根を枯らすのにも効果的です。
やり方は簡単。切り株の断面に除草剤を散布するだけです。もし、切り株の断面が枯れ切っている場合は、ドリルで全体的に穴を開け中まで薬剤が浸透するようにしましょう。
除草剤を使うときは、雨で薬剤が流れて効果が薄れてしまったり、他の植物が枯れてしまうことを避けるため、晴れが続く日を選んでください。
雨が心配な場合は、除草剤を塗った後に木の断面にビニールシートなどをかけて固定しておくといいですよ。
これで数か月待つと、根まで枯らすことができます。
伐採後の根を枯らす方法その2 ■腐葉土を敷き詰める
2つ目は、腐葉土を使います。除草剤を使う方法と比べて少し手順が多いですが、子どもやペットがいても安全に行える方法です。
①切り株が完全に枯れ切るまで待つ
②切り株にドリルで穴を開ける
③切り株の周りを囲う
④囲いと切り株の間に腐葉土を詰めていく
⑤腐葉土が乾かないように定期的に水をかける
この方法で、数か月~1年が経てば根は枯れます。
伐採後の根を枯らす方法その3 ■黒いビニールで覆う
3つ目は黒いビニールで覆う方法です。切り株に光が当たらないように、黒いビニール袋をすっぽりかぶせて固定します。
そうすることで、光合成ができなくなり枯れていくでしょう。時間はかかりますが、少しの手間でできる作業です。
ただし、ビニールをかけていることで湿気がこもります。そのため湿気が好きな害虫がよってくる可能性も。
定期的に、虫が発生していないかチェックしてくださいね。
やってはいけない木を枯らす方法
木を枯らす方法として、さまざまなアイテムが紹介されています。ですがその中でも、使ってはいけないものがあるのです。
・漂白剤
・シンナー
・塩化カルシウム
・塩
漂白剤やシンナーは、使用することで人やペットに害が出る可能性があります。また、除湿剤として使われる塩化カルシウムや塩は、土壌に成分が残留することが。
他の植物の生育にも影響を及ぼすことがあるので使わないようにしましょう。
枯らした木の処分方法
木を枯らす方法・根を枯らす方法を行い完全に枯れたら、木を処分しましょう。
自分でできる主な処分方法は2つ。
・木を小さく切り可燃ごみに出す
・焼却場に持ち込む
小さく切っておけば、多くの自治体で可燃ごみとして出すことができます。また、市区町村の焼却場に持ち込むことで処分できることもあります。
お住まいの地域によって決まりがあるはずです。ルールを確認して、処分するようにしてくださいね。
自分でできない場合は業者に依頼を
木を枯らす方法を試したけれどうまくできない…伐採や伐根まで自分でするのは無理…といった場合は、プロの業者に依頼しましょう。不要な庭木などを1日~数日で撤去してもらえます。
また、撤去した木の処分まで頼むことができるので処分方法に頭を悩ますこともありません。料金がかかっても楽に木の処分をしたい場合はプロに依頼することを検討してください。
では、業者に依頼するときのおおまかな費用相場とポイントを紹介します。
プロの業者に依頼する場合の費用相場 ■木の高さや幹の太さなどで金額は変わる
プロの業者に依頼した場合、木の高さによって料金設定がされていることが多いです。
おおまかな費用相場は下記のとおり。
・3m未満:3000円~10000円
・3m~5m:8000円~12000円
・5m以上:12000円~15000円
伐根までする場合は別途料金がかかることがあります。その場合は幹の太さや木の生えている場所、整地が必要かで料金が変動すると考えておきましょう。
5000円程から作業してもらえる場合もありますが、条件による部分が大きいので事前の確認が必要です。
プロの業者に依頼する場合のポイント ■事前の確認と見積もりが大切!
費用相場でもお伝えしましたが、業者によって「木の高さ・太さ・範囲」などで料金が違ってくることがあります。複数の業者で見積もりを取るようにしましょう。
また、伐採伐根や処分などどこまで対応してくれるかも確認しておくのがおすすめ。依頼してから対応範囲が少なかったといったことにならないよう注意してくださいね。