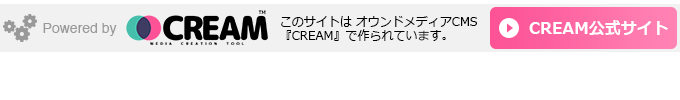蛍光灯のスイッチをONにしても電気がつかない時は、新品の蛍光灯に交換する方は多いのではないでしょうか? 『蛍光灯がつかない=蛍光灯を交換する』ことは当然の流れですが、新品の蛍光灯に交換しても何かしらの原因で電気がつかないことがあります。
新品の蛍光灯に交換しても電気がつかないと、頭の中ではどうして蛍光灯がつかないのか? 原因の追究が始まるはずです。"蛍光灯のつけかたを間違えた?" "新品の蛍光灯は不良品なのか?"など、考える方もいるでしょう。
蛍光灯がつかない原因はいくつもあり、蛍光灯がつかない原因をつきとめないと解決しません。今回は『蛍光灯がつかない時の原因』や『蛍光灯の交換方法』などをご紹介します。
蛍光灯が光る仕組み

蛍光灯が光る仕組みを知っていますか? 本来、蛍光灯が放つ光は目に見えるものではありませんが、蛍光管の中に白く濁った蛍光塗料を塗ることで明るい光に見える仕組みです。もう少し詳しく蛍光灯が光る流れを見ていきましょう。
蛍光管の中には水銀ガスが含まれていて、フィラメントと呼ばれている部分に高圧電力が流れると電子が発生して飛び出します。飛び出した電子は蛍光管の中に含まれている水銀ガスとぶつかると振動して、紫外線が放出される仕組みです。
蛍光管の中で発生した紫外線は蛍光灯に光を与え明るくします。紫外線は肉眼では見えませんが、蛍光管の中に白濁の蛍光灯塗料を塗ることで可視化され光に見えるわけです。白濁色の蛍光塗料に紫外線が当たると3原色(赤・緑・青)の光を放ち、蛍光管の中で3原色が混ざると白い光に見えます。
蛍光灯の種類

部屋を明るくしてくれる蛍光灯ですが、どれくらいの種類があると思いますか? 蛍光灯は4つの種類があり、家庭やオフィスなど幅広い場所で使われている蛍光灯もあります。4つの蛍光灯の種類を簡単にまとめました。
【蛍光灯の形状】
・直管型蛍光灯:横長の棒状の蛍光灯でオフィスや学校でもよく使われています。直管型蛍光灯は蛍光灯の中でも王道です。
・丸型蛍光灯:円形状の蛍光灯で自宅では和室で使うこともあります。丸型蛍光灯は直管型蛍光灯と同じく、様々な場所で使われているオーソドックスな蛍光灯です。
・コンパクト型蛍光灯:細くて短い蛍光灯が密集しているタイプや、横長の蛍光灯をU字に曲げたようなタイプがあります。
・電球型蛍光灯:電球の形状に似ていますが、蛍光管の部分はうねっていてスパイラルの形状が特徴的です。もしくは、見た目は電球とほぼ一緒のタイプもあります。
蛍光灯の寿命

蛍光灯がつかない時は寿命かもしれません。蛍光灯の寿命は蛍光灯の種類にもよりますが2年~4年くらいで、蛍光灯がチカチカしてつかない場合は蛍光灯の役目を終えたと思っていいでしょう。
蛍光灯が完全に寿命を迎えたサインを見極める方法は、蛍光灯の端が黒ずんでいるか?チェックすることです。蛍光灯の端が黒くなっていれば寿命を迎えています。
蛍光灯の寿命は早いと約2年で長くても約4年ですが、使い方によっては短命な蛍光灯になると思いましょう。蛍光灯が早く寿命を迎えるパターンは頻繁に電気のON/OFFをすることです。電気をつけたり消したりする行為は蛍光灯の負担となり寿命が短くなります。
蛍光灯がつかない原因4個

蛍光灯のスイッチをONにしても電気がつかない原因は必ずあります。蛍光灯がつかない時に考えられる原因は4つあり、蛍光灯のことをよく知らない方は初めて聞く用語もあるでしょう。では、蛍光灯がつかない原因をご紹介します。
■①蛍光灯が寿命を迎えている
蛍光灯がつかない原因でよくあるケースが蛍光灯の寿命です。蛍光灯の寿命について前項で説明しましたが蛍光灯は数年で寿命を迎えます。"あれ? 蛍光灯がつかない"と思ったら蛍光灯の寿命を疑い、蛍光灯の端の黒ずみを確認しましょう。
■②点灯管が寿命を迎えている
蛍光灯がつかない時は点灯管が寿命を迎えている可能性があります。点灯管の寿命は4年~8年くらいで、点灯管は蛍光灯を光らせるための着火剤のような存在です。
蛍光管の中のフィラメントに高圧電流が流れると蛍光灯は光を放ちますが、点灯管が寿命を迎えるとフィラメントに電流を流すことができません。
点灯管は小さな豆電球のようなもので、グロー管・グローランプ・常夜灯とも呼ばれている電気パーツです。ほとんどの蛍光灯には点灯管がついていますが、LED蛍光灯やインバーター式蛍光灯には点灯管はないため蛍光灯がつかない時は点灯管があるか? 確認しましょう。
■③安定器が壊れている
蛍光灯がつかない時は安定器が故障している可能性があります。安定器が故障して蛍光灯がつかない時は安定器の中にある部品、絶縁体・コイル・コンデンサーなど壊れていることが多いです。安定器の故障の原因は経年劣化などが考えられます。
安定器は文字通り、光を放っている蛍光灯を安定させたり蛍光灯を一定の明るさにキープする電気パーツです。安定器が不具合をおこすと電流を安定させることができず、蛍光灯がつかない・蛍光灯がついたり消えたりするなどの症状が現れます。蛍光灯や点灯管に異常がなく蛍光灯がつかない場合は安定器の故障を疑いましょう。
■④配線などに不具合がある
点灯管・安定器・蛍光灯に異常がなくても電気の配線など何かしらの異常があると、蛍光灯はつかないです。蛍光灯がつかない何かしらの原因は様々で、停電・配線や配電盤の故障・ブレーカーが落ちている・蛍光灯のスイッチが壊れているなど何点か考えられます。
蛍光灯が片方一本だけつかない原因2個

1つの照明器具に2本の蛍光灯を使うタイプがありますが、片方の蛍光灯だけつかないことはありませんか? 2本の蛍光灯が同時につかない時は、これからご紹介する内容をチェックして片方の蛍光灯がつかない原因をつきとめましょう。
■①片方の蛍光灯だけ先に寿命を迎えている
蛍光灯を2本使うタイプの照明器具で片方の蛍光灯だけがつかない場合は、つかない方の蛍光灯だけ寿命を迎えています(2本の蛍光灯を同時に設置した場合)。蛍光灯を2本同じタイミングでセットして照明器具を使うと、蛍光灯の寿命を迎える時期は2本ともほぼ変わりません。
ただ、同じタイミングで2本の蛍光灯をセットして照明器具を使っても、2本同時にピッタリ寿命を迎えるパターンはレアケースで少ないでしょう。ほとんどの場合は片方の蛍光灯が先に寿命を迎えると、もう片方の蛍光灯は数日後など大きな時間差はなく寿命を迎えます。
■②片方の点灯管が先に寿命を迎えている
先ほど点灯管の寿命について説明しましたが、片方の蛍光灯がつかない時は点灯管の寿命を疑いましょう。蛍光灯を2本使う照明器具に点灯管がある場合は点灯管も2つあります。点灯管の寿命もセットしたタイミングが同じであれば寿命を迎える時期もほぼ同じです。
2つの点灯管を同時に使う場合も蛍光灯を2本使う照明器具の寿命パターンと変わりません。1つ目の点灯管だけ先に寿命を迎えた後、2つ目の点灯管もさほど時間を空けることなく寿命を迎えます。
蛍光灯を新品に交換してもつかない原因4個

蛍光灯がつかない時に最初にする行動と言えば、"蛍光灯の交換"と答える方は多いはずです。蛍光灯を新しいものに交換すれば電気がつくはずですが、新しい蛍光灯に交換しても電気がつかないこともあります。新品の蛍光灯で電気がつかない原因を見てみましょう。
■①蛍光灯の型番が間違っている
蛍光灯の型番が間違っていると新品の蛍光灯でもつかないです。新品の蛍光灯に取り替える時は蛍光灯の型番を確認してから照明器具にセットするのが基本ですが、蛍光灯の型番の確認ミスをする方もいます。
蛍光灯の交換作業に慣れていない方や、蛍光灯の型番の見方がわからない方は正しい型番の蛍光灯をチョイスできないことも珍しくありません。
■②蛍光灯の接続不良
新品の蛍光灯に変えても電気がつかない原因でよくあるのが、蛍光灯の接続が上手くできていないことです。新品の蛍光灯をセットして蛍光灯がつかない時は、蛍光灯の接続部分がしっかりハマっているか? チェックしましょう。
蛍光灯の接続不良だけが原因で電気がつかない場合は、蛍光灯の接続部分がかみ合えば電気がつきます。
■③蛍光灯が不良品
新品の蛍光灯でも不良品であれば電気はつかないです。新品の蛍光灯が不良品のケースはあまりないことですが、不良品の蛍光灯が流通している可能性はあります。
不良品の蛍光灯なのか? 確認するなら別の蛍光灯で新しいものを設置して試してみましょう。別の蛍光灯で電気がつくなら、最初にセットした新品の蛍光灯は不良品だと判断できます。
■④照明器具が壊れている
蛍光灯がつかない照明器具は10年以上使っていますか? 照明器具を長く愛用している場合は照明器具の故障が原因が関係しているかもしれません。照明器具が故障していれば新品の蛍光灯に交換しても電気はつかないです。
照明器具も10年以上使っていれば配線コードを覆っているゴムなどが劣化します。配線コードを覆っているゴムが劣化している場合は漏電していることもあるでしょう。照明器具の配線が漏電していれば新品の蛍光灯に交換しても電気がつかないのはもちろんですが、こわいのは火災や感電です。
蛍光灯の交換方法

蛍光灯の交換方法がよくわからない方は、これからご紹介する内容をチェックしましょう。今回は蛍光灯を外すやり方をメインに説明しますが、新品の蛍光灯を照明器具にセットする時は外す時と同じ流れで行います。
蛍光灯の交換作業を安全に行うために必ず蛍光灯のスイッチをOFFにしてください。蛍光灯のスイッチをONにしたまま蛍光灯の交換作業をすると、蛍光灯を接続した時に光がまぶしいのと手に熱が伝わり熱いです。
ブレーカーを落とす必要はないですが、蛍光灯のスイッチは必ず切ってから蛍光灯の交換作業を行いましょう。
■直管型蛍光灯
直管型蛍光灯のソケット部分の形状はいくつかあります。切り込みタイプ・はめ込みタイプ・防水キャップがついているタイプ・カバーがついているタイプなど様々です。
直管型蛍光灯のソケット部分の形状は様々なタイプがありますが、よくある形状は『切り込みタイプ』と『はめ込みタイプ』と思いましょう。では、直管型蛍光灯のソケット部分のタイプ別に蛍光灯を交換するやり方をご紹介します。
【切り込みタイプ】
蛍光灯を持ったら前か後ろに90度回し、自分の方に向かって蛍光灯を引っ張ると外れます。
【はめ込みタイプ】
はめ込みタイプは蛍光灯をバネで固定する仕組みです。蛍光灯の片側のソケット部分だけを押しつけてつかない蛍光灯を外します。
【防水キャップがついているタイプ】
防水キャップがついているタイプは水の侵入を防ぐために、蛍光灯の両端にキャップがついているのが特徴です。つかない蛍光灯を外す時は最初にキャップを緩めますが、外したキャップは床に落とさないよう注意しましょう。理由は外したキャップを床に落とすと欠けてしまうからです。
キャップを緩めたら蛍光灯を持って照明器具の真ん中に寄せます。次に、切込みタイプやはめ込みタイプの蛍光灯を外す時と同じ流れで、防水キャップがついているタイプの蛍光灯を外しましょう。
【カバーがついているタイプ】
蛍光灯にカバーがついているタイプは少ないですがまれにあります。蛍光灯を覆っているカバーを蛍光灯の両サイドから真ん中に向かって押して外すか、蛍光灯を覆っているカバーを外側にズラせば外れます。
■丸型蛍光灯
丸形蛍光灯はプラグに差し込むと電気がつく仕組みで、蛍光灯の交換作業は1パターンしかありません。つかない丸形蛍光を外す時は蛍光灯を支えている金属のカバー(ソケット)から抜き出してから、新品の蛍光灯の交換作業を行います。
金属のカバー(ソケット)を外すやり方は片方の手で蛍光灯を持って支えたら、もう片方の手で金属のカバー(ソケット)をつかんでつかない蛍光灯を抜き出しましょう。金属のカバー(ソケット)からつかない蛍光灯がなかなか外れない時は、蛍光灯を軽く左右に揺さぶりながら外します。
新品の丸形蛍光灯をセットする時は、蛍光灯とプラグがしっかりハマるよう少し圧をかけるのがポイントです。蛍光灯に力を加えて圧をかけると壊れそうですが、プラグ部分はプラスチック製のカバーで保護されているため蛍光灯は簡単に壊れません。
■コンパクト型蛍光灯
コンパクト蛍光灯は細い蛍光灯が何本かセットになっている状態のタイプや、U字に曲がっている蛍光灯などありますが、つかない蛍光灯を外して新品の蛍光灯に交換する作業は簡単です。ソケットを引っ張ればつかない蛍光灯は外れます。
■電球型蛍光灯
電球型蛍光灯は他のタイプの蛍光灯と違い、バネで固定したりプラグを差し込むことはありません。電球型蛍光灯のソケットにはじゃばら状の溝があり、蛍光灯を手で持って左にクルクル回すと簡単に外れます。新品の蛍光灯を設置する時は右に回すとセットできる簡単構造です。
ほとんどの電球型蛍光灯は左に回すと外れて右に回すとセットできますが、一部の蛍光灯は逆のパターンもあります。
蛍光灯をクルクル回して外したり設置するタイプは、照明器具に新品の蛍光灯をセットする時の注意点があるため覚えておきましょう。蛍光灯をセットする時に回しすぎるとソケットが壊れる可能性があります。蛍光灯を回して動かなくなったら回すのをやめましょう。
■点灯管
蛍光灯の点灯管がつかない場合はもちろん新品に交換しますが、点灯管がついていても交換しましょう。点灯管は蛍光灯よりも寿命が長いですが、メーカーは蛍光灯を交換するタイミングで点灯管も一緒に交換することをススメています。
点灯管の交換方法はシンプルです。つなかい点灯管をクルクル左に回して外し、新品の点灯管をつける時は右に回すと設置できます。
まとめ
蛍光灯がつかない原因は10個ありますが、意外と多いと感じた方もいるのではないでしょうか? 蛍光灯がつかない原因でよくあるのが蛍光灯が古く寿命を迎えているケースと、新品の蛍光灯を設置した時に接続部分がハマっていないケースです。
蛍光灯がつかない時はよくある原因からつぶしていき、消去法式で解決していくといいでしょう。蛍光灯がつかない原因をつきとめれば、蛍光灯は再び明るい光を放つようになります。