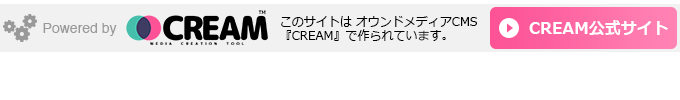毎日家族が踏んでいるカーペット、なんだか黒ずんだりニオイが気になったりしてきてませんか?
ホコリやダニの温床になったカーペットは、不潔なだけでなく気管支炎やアレルギーの原因になることも。正しい掃除方法を知って、すっきり爽快なお部屋を手に入れましょう。今回は、自宅でできるカーペットの掃除方法を5ステップに分けてご紹介します。
カーペットの正しい掃除方法

毎日、掃除機をかけているだけのカーペットには、知らず知らずのうちに汚れやゴミ、ホコリが溜まっていくものです。汚れた部分をやみくもにゴシゴシこすっては、カーペットの汚れを押し広げてしまうだけになることもあります。まずは正しい掃除方法を知って、カーペットをすっきりきれいにしましょう。
■1.カーペットのゴミやホコリを取る
まず、掃除機を丁寧にかけて、カーペットに落ちた小さなゴミやホコリを取ります。家具と家具の間やテーブルの下は、特に念入りにかけましょう。カーペットの毛流れに逆らうようにして、いろんな方向からかけることで、奥に入り込んでいるゴミやホコリが吸い取りやすくなります。
特にパイルの敷き込みカーペットは、毎日踏まれることで毛足が完全に寝てしまっていることがほとんどです。寝ている方向に逆らうように掃除機をかけて、毛足をできるだけ起こしてやるようにしましょう。
また、ペットの毛や髪の毛は、カーペットの細い毛に絡まりやすくなっています。掃除機をかける前に目の粗いブラシで毛並みを起こしてやると、ゴミ等が浮き上がってきます。
■2.カーペットのゴミを取るこんな裏技も
掃除機では取り切れない細かいゴミやホコリは、ゴム手袋と重曹スプレーを使うのがおすすめです。重曹を溶かして容器に入れたものを、カーペット全体に薄くスプレーします。そして、厚手のゴム手袋をつけた手でカーペットをこすると、面白いようにゴミがついてきます。薄手のゴム手袋では破れやすいので、厚手のものを使うのがコツです。
掃除機をかけたあとでも、大量のゴミや髪の毛が残っていることに驚かれるでしょう。毎日掃除をしているつもりでも、カーペットに絡みついた毛や奥に入り込んだゴミは取れていないということですね。この方法だと、複数の人が作業することも可能なので、お子さんに手伝ってもらうこともできますね。
■3.カーペットの汚れを落とす
落ちているゴミやホコリを取りきったら、こびりついている汚れを落としましょう。カーペットを見わたしてみると、食べこぼしやペットの嘔吐、いたずら書きの跡等が残っていませんか?拭き残した汚れも、この際きれいに落としたいもの。
汚れを落とす方法は、水性と油性で異なります。誤った対処をすると、汚れが落ちないばかりか、一層汚れを広げてしまうことにもなるので注意が必要です。時間をおいた汚れは落ちにくくなっていますが、根気よく落としていきましょう。
■4.水性の汚れの場合
水性の汚れを落とすには、ぞうきんに薄めた中性洗剤やクエン酸、重曹液をしみこませたものを使います。汚れた部分を水分を含ませるイメージで、根気よくトントンと叩きます。ある程度汚れが落ちてきたら、今度は乾いたぞうきんで叩いて水分を吸い取っていきます。
洗剤液に含まれた汚れを全て吸い取る気持ちで、何度も乾いたぞうきんを取り替えて拭きます。ゴシゴシこすると、汚れを含んだ水分が広がってしまいますので、狭い範囲をトントン叩くようにしましょう。
■5.油性の汚れの場合
油性マジックや油を含んだ食品の食べこぼし等は油性の汚れですので、ベンジンを使って落とします。ベンジンは油を溶解させる特性のある薬品で、着物等の気軽に洗えない衣類のシミ抜きによく用いられています。
水性の汚れと同じように、ベンジンを含ませたぞうきんで汚れた部分をトントンと叩いて落としていきましょう。手順としては水性の汚れと同じですが、ベンジンを使う際には気を付けなくてはならないことがいくつかあります。
【火気に注意】
ベンジンは引火性の強い薬品です。火気にはくれぐれも注意しましょう。
【換気をする】
小さなお子さんやペットが揮発したベンゼンを吸わないよう、換気を充分にしましょう。
【色落ちに注意】
ベンゼンは汚れと一緒にカーペットの色も落としてしまう恐れがあります。使う前に目立たないところでテストすることをおすすめします。
■カーペットの汚れを落とすときのコツと注意点
カーペットの汚れを落とすときは、汚れを落としたい場所の裏側にも乾いたぞうきんを敷いておくようにしましょう。床に洗剤やベンジンがつくと、色落ちや破損の原因になることがあります。また、どちらの場合も完全に乾くまで根気よく拭きましょう。必要以上に力を入れる必要はありません。根気よく何度もトントン叩いて水分を吸い取ります。
ある程度乾いたら、目の粗いブラシとドライヤーで毛を起こしながら乾かすのもおすすめです。毛足の長いカーペットは水を含むと、束になってぺたっと寝てしまいますが、ドライヤーを使うと毛足を起こしてふんわりとした仕上がりにできます。
ブラシをかけられないパイルカーペットは、裏側からドライヤーの温風を当ててやると毛足を起こすことが出来ますよ。
カーペットを汚してしまったときの部分洗い方法

カーペットを汚してしまった!そんな時はザブザブ丸洗いしたいところですね。でも、大きなカーペットや敷き込みカーペットではそうもいきません。ここでは、カーペットの汚れた部分だけを洗う方法をご紹介します。
■汚れに水分を含ませる
最初に、乾いたキッチンペーパー等で汚れを拭き取りましょう。汚れた部分をつまんで持ち上げるイメージで、できるかぎり汚れを拭いておきます。こうすると、後の部分洗いがかなり楽になりますよ。汚れた部分を広げないことを意識しながら拭いていくと良いでしょう。
使うのは中性洗剤を薄めた液をしみこませたぞうきんです。汚れた部分に洗剤をしみこませるように拭いていきます。汚れがカーペットに戻らないよう、常にきれいな面を使って拭くのがポイントです。
■浮いた汚れを叩いて拭き取る
洗剤がまんべんなくしみ込むと汚れが浮き上がってきますので、乾いたぞうきんで吸い取っていきます。ここでもトントンと軽く叩きながら、決してこすらずに拭き取りましょう。汚れ落ちが悪いと感じたら、また洗剤をしみ込ませて汚れを浮き上がらせます。この時にお湯を使うと、より汚れ落ちが良くなります。
■汚れを一気に吸い取る
ある程度汚れが落ちたら、いよいよ仕上げです。水分を出来る限り吸い取ったら、乾いたぞうきん(できるだけ分厚いもの)を乗せます。そして、その押し当てた部分にヘッドをはずした掃除機を押し当てて吸い取りましょう。カーペットに残った汚れと水分が、掃除機に吸い上げられてぞうきんにしみ込んでいきます。ある程度吸ったら、乾いたぞうきんに取り替えてきれいに汚れを吸ってしまいましょう。
■掃除機で吸い取るときの注意点
掃除機で水分を吸い取る時には、出来るだけ分厚いものを使うようにしましょう。カーペットから吸い上げられた水分がぞうきんを貫通すると、掃除機の中に水分が入ってしまいます。故障や感電の原因になって危険ですので、くれぐれも注意してくださいね。
分厚いぞうきんがない場合は、薄手のものを2枚重ねにして、間にキッチンペーパー等を挟みこむのもおすすめです。どの場合も、何度もぞうきんを取り替えて、常に乾いた面を掃除機に当てるようにしましょう。
■部分洗いに向かないカーペット
ペルシャ絨毯や手染め等の、色落ちしやすいカーペットは部分洗いに向きません。品質表示をよく確認してから洗うようにしましょう。色落ちしやすいカーペットを洗いたい場合は、専門のクリーニング業者に相談してみるのが無難です。
あると便利なお手入れグッズ

カーペットの掃除は、家事の中でもけっこうな大仕事です。でも、ちょっとしたグッズを揃えることで手間を格段に減らすことができますよ。カーペット掃除に使える、便利なお手入れグッズをご紹介します。
■スチームモップ
蒸気の力で掃除するスチームモップは、カーペットだけでなく家中の掃除に大活躍の家電です。たいていの汚れは熱に弱く、カーペットも例外ではありません。洗剤を薄くスプレーしてスチームモップを当てると、汚れがどんどん浮き上がってきます。
部分洗いにも使えますし、掃除機等でホコリとゴミをきれいに取ったカーペット全体を、スチームモップで拭くのもおすすめです。洗いたてのような香りとフカフカ感が最高ですよ。ただし、スチームモップはその特性上、熱に弱い素材の掃除には向きません。使用する前に、品質表示をよく確認することをおすすめします。
■ゴム手袋
カーペットの間にもぐりこんだ小さなゴミや絡みついた髪の毛を取るのに、ゴム手袋は欠かせません。掃除機では取り切れない部分までしっかりと掃除できます。騒音も少ないので、思い立った時にできるのも嬉しいですね。カーペット掃除専用に、一組は揃えておきたいアイテムです。
■スプレー容器
カーペットの掃除には、薄めた中性洗剤やクエン酸、重曹水等を使用します。広い面積を掃除するのであれば、あらかじめ洗剤液を作っておきましょう。まんべんなく薄くスプレーするのに、スプレー容器があるのとないのでは大違いです。
■重曹
どんな掃除に使えるといっても過言ではない重曹ですが、カーペット掃除にも大活躍します。掃除機をかける前に重曹を振りかけておくと、カーペットにしみついたニオイをきれいに消すことができます。毛足に残った重曹の粉を取るには、固くしぼったぞうきんで水ぶきすれば大丈夫ですよ。
ナチュラル志向の方であれば、クエン酸と重曹、ティーツリーの精油で自家製の洗剤も作れます。この洗剤でカーペットを拭くと、お部屋にほんのり良い香りが漂いますよ。
汚れ以外のカーペットお手入れ方法

忘れがちですが、カーペットは布製品です。敷きっぱなしだと、いやなニオイやダニの発生の原因になることも。掃除機をかけているだけでは、ニオイやダニは駆除できません。ここでは、汚れ以外のカーペットのお手入れ方法をご紹介します。
■カーペットのダニを殺す方法
適度な温度と湿度が保たれたカーペットは、ダニの温床です。ダニはアレルギーやじんましん、気管支炎の原因にもなる厄介なものです。しっかり退治しましょう。ダニは掃除機で吸っても、30%ほどしか駆除できないと言われています。ダニの駆除に最も有効なのは、熱を与えることです。
50度ほどで、ほとんどのダニは死滅すると言われています。一番良いのは乾燥機の中にいれてしまうことですが、敷き込みカーペット等ではそうもいきませんね。その場合は、スチームアイロンを使ってダニを退治します。アイロンのスチームを出しながら、カーペットの端から端までしっかりと蒸気を当ててやります。
当ててない部分があると、そこにダニが逃げ込んでしまいます。全面にまんべんなくスチームを当てましょう。とはいっても、広いカーペット全面にアイロンをかけるのは重労働です。そこで、先ほどご紹介したスチームモップの出番です。
スチームモップからは、最高70度にもなるスチームが出ています。ダニを退治するには充分な温度ですね。熱を加えると、カーペットの毛足も立ち上がるので仕上がりはふわふわです。仕上げに掃除機を丁寧にかけて、ダニの死骸を吸い取りましょう。
■カーペットの臭いを消す方法
「カーペットの上にゴロンと横になると、なんだかニオイが気になる……』毎日家族が足で踏んでいるのですから、当然と言えば当然ですよね。ニオイを消すために消臭スプレーを使っている方もいるかもしれませんが、根本的な解決にはなりません。
ニオイの根元を絶つには、これも先ほどご紹介した重曹がおすすめです。掃除機をかける前に、重曹の粉をまんべんなく振りかけて小一時間放置します。そのあと、いつものお掃除をすればニオイがすっきり取れますよ。
粉を振りかけるのが難しい場所に敷いてあるカーペット等では、濃いめの重曹液をつけたぞうきんで拭きあげるのもおすすめです。どちらの場合でも、あとでしっかり重曹を拭き取るようにしてくださいね。
まとめ
家族のくつろぎに欠かせないカーペットやラグには、毎日少しずつ汚れが溜まっていきます。季節に一度は、家族総出でカーペットをしっかり掃除しておきたいもの。心おきなく床に寝転がれる、清潔なリビングルームを目指しましょう!

カーペットの家庭での洗濯方法についてまとめています。自宅で洗濯できるカーペットの見分け方や、シミや汚れを綺麗に取るためのコツを説明しているほか、カーペットを洗濯機で洗う方法と、お風呂で洗う方法、そして早く乾く干し方についても解説しています。