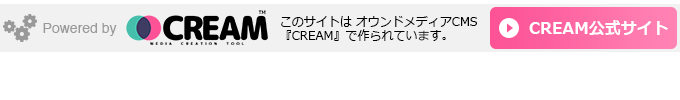普通の洗剤で落ちなかった汚れも、漂白剤ならスッキリとキレイにしてくれるかもしれません。キッチンのまな板やフキンを除菌したり、洗濯で使用したりと、漂白剤は身近な洗剤です。漂白剤は何に使うかで、種類を選ぶ必要があります。そのため、少し使いにくいイメージがありますが、一度覚えてしまえば区別できるようになりますよ。
液体の漂白剤と、粉の漂白剤とがあるのは何となく理解しているけれど、それぞれどう違うか知っているでしょうか?ここでは漂白剤の種類と、それぞれの用途、そしてキッチンや洗濯での漂白剤の使いこなし方について説明します。
酸素系漂白剤のキッチンでの使い方5つ

■①酸素系漂白剤を「電子レンジ」の掃除に
電子レンジの中の汚れは、食品が熱でかたまってしまい、なかなか取れませんよね。そのような時は酸素系漂白剤の出番です。ぬるま湯1リットルに小さじ1杯程度の酸素系漂白剤を溶かして、雑巾を絞ります。電子レンジの中には食品を入れるので、洗剤のニオイがついてしまうのは避けたいものです。その点、酸素系漂白剤であればニオイがしないので、掃除と除菌に最適です。
■②酸素系漂白剤を「冷蔵庫」の掃除に
冷蔵庫も電子レンジと同じように、食品を入れる場所なので、ニオイの強い洗剤は使えません。酸素系漂白剤はニオイがしない上、除菌や殺菌ができるので冷蔵庫の掃除にぴったりです。ぬるま湯1リットルに小さじ1杯程度の酸素系漂白剤を溶かします。酸素系漂白剤を雑巾につけて、冷蔵庫の棚板や扉のポケット、照明部分やチルド室、冷凍庫や野菜室などを拭き掃除しましょう。食中毒が気になる梅雨の前にやると良いでしょう。
■③酸素系漂白剤を「食器洗い機・食洗機」用の洗剤に
食器洗い機はニオイがこもりがちですが、酸素系漂白剤を洗剤として使うことで、嫌なニオイから解放されます。使用する量は、4~5人用の食器洗い機で、小さじ1杯の酸素系漂白剤を使用します。もし汚れがひどいようであれば、量を足してください。
酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)がお湯に溶けると、過酸化水素が発生します。過酸化水素は、水と活性酸素でできています。この活性酸素によって、汚れが落ちるのです。過炭酸ナトリウムが過酸化水素を失うと、炭酸ソーダになりお湯の流れを強力にして、汚れが落ちるのを助けます。このような仕組みで食器の汚れをキレイにしてくれるのです。
■④酸素系漂白剤に「水筒のフタ」をつけ置く
水筒のゴムパッキンや、口をつける部分などは、なかなか汚れが落としにくい部分です。複雑な形をしているものや、洗いにくいものは、酸素系漂白剤の力をかりましょう。お湯1リットルにつき、酸素系漂白剤を大さじ二分の一入れて溶かします。お湯はお風呂くらいの温度がベストです。
■⑤酸素系漂白剤で「まな板の除菌」
酸素系漂白剤にお風呂位の温度のお湯を加えて、マヨネーズ程度のペースト状にします。まな板にハケで酸素系漂白剤ペーストを塗っていきます。特に気になる汚れの部分は重点的に塗ります。ペーストが乾いてきたら、粉末の酸素系漂白剤をスプレーにしたものを吹きかけて再びペースト状にします。2時間ほどそのままにした後、スポンジやタワシで洗ってキレイにすれば完了です。
酸素系漂白剤を洗濯で使う3つのコツ

■①先に洗ってから酸素系漂白剤で漂白
酸素系漂白剤は、お風呂位の温度のお湯で使用するのがベストです。黄ばんできてしまった服や、シミがついてしまったシャツなど、普通の洗濯では落ちない汚れも、酸素系漂白剤を使用すると綺麗になります。洗濯で使うコツとしては、先に別の洗剤で洗濯して脱水まで済ませ、その後に酸素系漂白剤を溶かしたお湯につけておきましょう。1時間位、酸素系漂白剤を溶かしたぬるま湯につけたら、すすいで絞った後、天日干しにします。
■②酸素系漂白剤にはウールはNG
ウールのマフラーなど、動物の繊維でできたものに漂白剤を使用すると、せっかくフワフワしていた手触りが失われてしまうことがあります。酸素系漂白剤でも、ウールに使えるものもありますが、きちんと説明書きを読んでから使うようにしましょう。
■③酸素系漂白剤は「シミ抜き」もできる
酸素系漂白剤はシミ抜きもできます。まず、シミがついてしまった部分を広げます。そして、シミがついた部分に、粉の酸素系漂白剤を乗せていきます。少し多いかなと思う位で丁度いい量になります。下にお皿などを置いておくと良いでしょう。
シミの上に盛った酸素系漂白剤の上から、40度から50度のお湯をスプーンなどで少しずつたらしていきます。粉がとけなくてもかまいません。そのまま15分程度置いておきます。もし水分が無くなって乾いてきたら、またスプーンでお湯を足してください。シミが落ちたら、普通に洗濯をします。
こんな場所にも使える酸素系漂白剤

■①酸素系漂白剤をシリコンが黄色くなってきたところに
シリコンは時間が経つにつれて、だんだんと黄色く変色してしまいます。もう買い換えないとダメなのかなと思ったら、酸素系漂白剤につけてみましょう。40度のお風呂くらいのお湯1リットルにつき、大さじ二分の一の酸素系漂白剤を入れて溶かします。そして黄色くなってしまったシリコンを一晩程度つけておきます。その後、何日か日光に当てると黄ばみが取れます。
■②酸素系漂白剤を「洗濯槽の掃除」に
お風呂のお湯程度か、少し熱い50度位のお湯に、酸素系漂白剤を投入します。お湯が10リットルにつき、酸素系漂白剤は100グラムとおぼえましょう。お湯は、なるべく上のほうまで入れたほうが、洗濯槽の裏にあるカビが取れます。
最初は「洗い」のコースで5分ほど回します。その後、しばらく何もしないでおいて、30分後に再び「洗い」のコースで5分ほど回します。これを2、3回繰り返します。そして、排水せずに一晩そのままにしておきます。
次の日の朝、ゴミやカビが浮き出ているので、網などで取り除きましょう。ゴミやカビをそのまま流してしまうと、排水口が詰まってしまう恐れがあります。最後にもう一度「洗い」で5分回したら排水します。その後、今度は水を入れてすすぎをします。
ゴミやカビが出てこないようになったら、掃除の完了です。
洗濯槽掃除のオススメの記事はこちら
↓

■③酸素系漂白剤で「カビ」を除去
酸素系漂白剤と石灰で、カビを除去します。石灰は消石灰(水酸化カルシウム)や生石灰(酸化カルシウム)を使います。消石灰であれば、ホームセンターで販売されています。消石灰は粉が空中に舞いやすく刺激物でもあるので、目や口に入らないようマスクやゴーグルをしておきましょう。
まず、消石灰10グラムを入れた容器の中に、50度から60度のお湯を30ml入れます。よくかき混ぜた後、酸素系漂白剤40グラムを入れます。よくかき混ぜて、マヨネーズ程度のゆるさにします。これで強力カビ取り剤の出来上がりです。
このカビ取りペーストを、気になるカビの部分に塗ります。ペーストを作った後、時間が経てば経つほど、カビを取ってくれる成分が抜けていってしまいますので、手早く塗ることが大切です。カビの部分にペーストを塗ったら、2時間程度そのままにしておきます。その間にペーストに水分が無くなって来たら、炭酸ソーダ水やセスキ炭酸水をスプレーでふきかけてポロポロにならないようにします。
2時間経ったら、スポンジなどで優しくペーストを取り払って完成です。よくカビが落ちて便利だからといって、作り置きはしないようにしましょう。ペーストの中の酸素が抜けてしまうと、カビを取ってくれる成分が無くなってしまうからです。
酸素系漂白剤を使う時の注意点3つ

■①酸素系漂白剤は「草木染め」の衣類に使える?
草木染めの服やスカーフなど、草木染めでできているものは、酸素系漂白剤と相性が悪いので気をつけましょう。草木染めを作る過程で、鉄や銅といった金属成分を使用することがあります。そして、金属と酸素系漂白剤が反応して布を痛めてしまうのです。草木染めには使わないようにしましょう。
■②酸素系漂白剤は、他の薬品と混ぜるのは危険
塩素系漂白剤のボトルには、よく「まぜるな危険」と書いてあります。塩素系漂白剤は、キッチンの掃除や除菌、トイレ掃除で使われることが多いのですが、酸性の漂白剤と絶対に混ぜないようにしましょう。
色々な種類の漂白剤を入れれば、もっと漂白できると思って塩素系漂白剤と、液体の酸素系漂白剤を混ぜてしまうと大変に危険です。また、塩素系漂白剤とクエン酸やお酢などもまぜると有毒なガスが発生してしまいます。
液体同士を混ぜていなくても、酸性の洗剤を入れていた容器に、そのまま塩素系漂白剤を入れてしまっても危険です。塩素系漂白剤を別のボトルに入れる時は、必ず同じ入れ物にいれて他のものは入れないようにしてください。
■③色移りには漂白剤はNG?
衣類に他の洗濯物の色がついてしまった場合、漂白剤で落としたくなってしまいますが、漂白剤ではなくお湯と洗剤で落とすことが可能です。色移りした原因は衣類の染料になるため、50度程度の熱めのお湯に、通常の倍の量の洗濯洗剤を入れて洗います。色移りの時に使用する洗剤は、液体洗剤よりも粉末洗剤のほうが強力なのでよく落ちます。
酸素系漂白剤と塩素系漂白剤の違いは?漂白剤の種類4つと成分

漂白剤は、大きく分けて4タイプあります。
それぞれについて見てみましょう。
■①「塩素系」漂白剤(液体)
アルカリ性の漂白剤で、主な成分は次亜塩素酸ナトリウムです。漂白剤の中で、一番漂白する力の強いのが、塩素系漂白剤です。殺菌力や除菌力もあります。主に、白い繊維のものに使用します。
また、カビ取り剤として使ったり、タイルの目地に色がついた時や、台所、浴槽、トイレの掃除に使用するなど、家の中でフル活躍する漂白剤です。効き目が強い分、繊維を痛めやすいので、いつも使用していると布がだめになってしまうこともありますので注意が必要です。
繊維の染料まで漂白する力を持っているので、色柄物には使用できません。また、ウール製品や、シルク製品、ナイロンやポリウレタン、アセートのような化学繊維にも使用できません。
入れ物に「まぜるな危険」と書かれていることが多く、酸性の粉末や液体などと反応すると、塩素ガスが発生してしまうので注意しましょう。塩素のニオイが強いので、使用する時には十分に換気を行って使ってください。
■②「酸素系」漂白剤(粉末)
弱アルカリ性の漂白剤で、主な成分は過炭酸ナトリウムです。4種類の漂白剤の中で、2番めに漂白力があります。食器洗い機用の洗剤としても使われていて、殺菌力や除菌力もあります。水に溶けると活性酸素が出てきますが、その時の力で頑固なシミを除去してくれるのです。
塩素系漂白剤のように、柄物の色を漂白してしまうことは無いので、色物柄物に使用できます。布や服をつけおき漂白する時は、繊維を痛めないので、こちらの漂白剤が向いています。ウール製品やシルク製品には向いていません。塩素系漂白剤のように、ツーンとする塩素のニオイが無いので使いやすい漂白剤です。洗濯槽の掃除の時に使ったり、排水口を殺菌する時にも使われます。
■③「酸素系」漂白剤(液体)
弱酸性の漂白剤で、主な成分は過酸化水素です。消毒液のオキシドールと使い方が似ています。4種類の漂白剤の中で、3番めに漂白力があります。殺菌力や除菌力があります。
こちらも塩素系漂白剤のように、色がついた繊維を漂白してしまうことは無いので、色柄物の漂白に使用できます。酸素系漂白剤を色柄物に使用すると、柄や色がはっきりします。
■④還元型漂白剤(粉末)
弱アルカリ性の漂白剤で、主な成分は二酸化チオ尿素とハイドロサルファイトです。業務用の漂白剤で、鉄分によって黄色くなってしまった白い服などを漂白するのに使います。色柄物には使用できないので、白い繊維でできたものにだけ使用できます。ほかの3種類の漂白剤は殺菌力や除菌力がありますが、還元型漂白剤には殺菌力や除菌力はありません。
■漂白剤を使えないのは?
どの漂白剤も、水洗いできるものにだけ使うことができます。水洗いできないものは、壊れたり傷つけたりする危険性がありますので、使用しないでください。また、金属のボタンや、服についているファスナーなども、どの漂白剤も使えません。
まとめ
じょうずに漂白するには、お湯を使うことと、長時間つけておくことがポイントです。酸素系漂白剤は、お風呂位の温度だと一番効果を発揮します。大きな布や衣類を漂白したい時には、浴槽を使って漂白すると効果的です。酸素系漂白剤を溶かしたお湯が早く冷めてしまわないように、お風呂のフタをするのも良いでしょう。
酸素系漂白剤は、塩素系漂白剤よりも刺激も少なく優しい漂白剤です。しかし、それでも色柄物をどれだけ痛めてしまうかわからないので、最初は目立たない場所に少しだけつけてみてください。
5分後ほど放置して、色が変わったり、他のものに色がついてしまったら、酸素系漂白剤を使うのは止めておきましょう。
簡単に除菌や殺菌をしてくれる酸素系漂白剤は、使いこなせば家中が清潔でキレイになります。ニオイも取ってくれるので、梅雨前に活用してほしい漂白剤です。

過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)で洗濯槽のカビを退治するポイント4つ
https://taskle.jp/media/articles/125過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)を使って、洗濯槽の裏にゴッソリ繁殖している黒カビをキレイにする方法をまとめました。